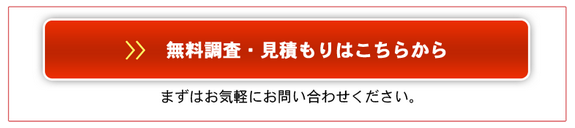長雨のあとに知らないうちに大量発生しているヤスデ。
ブロック塀に群がったりや家に侵入したりして問題を起こしているヤスデ。
グロテスクな見た目、潰したときの強烈な異臭を発することなどで嫌われているヤスデ。
不快害虫であるヤスデに遭遇しないために、「どのような対策」を、「どのタイミング」でやればいいのでしょうか?
事前に対策をとることで、ヤスデを侵入させないようにしていきましょう!
ヤスデってどんな虫?
対策をするためには敵を知ることも大切です。
まずはヤスデについてすこし知識を入れておきましょう。

日本には200種以上のヤスデが存在していますが、よくみかけるのは「ヤケヤスデ」という種類です。
| 活動時期 | 4月~10月 |
|---|---|
| 体長 | 20~80mm |
| 寿命 | 4~5年 |
| 歩き方 | まっすぐ歩く |
| 毒性 | ほぼ無毒 |
| 食性 | 腐植食性 |
ヤスデは、何もしなければ害を及ぼさない人畜無害な虫です。
噛まれる心配はありませんので、ムカデに比べると比較的取り扱いやすい虫だと言えます。
触るとダンゴムシみたいに丸くなるのも特徴です。(球体にはなりませんが)
ただし、強い刺激を与えたり、潰したりすると、強烈な刺激臭を発生させます。
ヤスデの体液には毒性が含まれており、素手で触ると、ヒリヒリとした痛みを受けるので注意しましょう。
ヤスデ対策のコツはヤスデが大量に発生する理由にあり!

基本的にヤスデは土の中や落ち葉の下に生息していますから、普段生活していてヤスデに遭遇した!ってことはあまりないと思います。
ヤスデが最も大量発生する時期は、梅雨の時期(6月~7月初旬)です。
2番目は、秋雨の時期(9月~10月)になります。
この2つの時期に共通する自然現象といえば・・・?
答えは「長雨」です。
ふだんはジメジメした湿気の多い場所を好むヤスデですが、さすがに水浸しの環境となると話は別のようです。
長いこと雨が降り続いていると、土の中だけでなく、土の表面にまで水がたまってきます。
水攻めにあったヤスデは溺れないようあわてて土からはいあがってきます。
そのときたまたま家があれば、壁をよじ登り室内に侵入してくるというわけです。
ということは、長雨の影響でヤスデが溺れるような危機的状況にならなければ、土の中から出てくることはなくなるでしょう。
「水はけをよくすること」がヤスデを大量発生させないポイントになります。
ヤスデ対策その1「水はけをよくする」
水はけをよくすることで、ヤスデが土からはいあがる原因を取り除くことができそうなのは分かりました。
ただ、水はけの改善ってすごくお金がかかりそうなイメージがありますよね。
実際に業者に依頼したら結構な費用がかかるでしょう。
しかし、業者に頼まなくても水はけを改善できる方法があります。
自分でもやれる水はけをよくする方法をご紹介します。

そもそも、水たまりができる原因ってなんでしょう?
水が土の中にしみこむことができないからと考えがちですが、水たまりができる原因は、地表の水の流れにあります。
地表を移動する雨の量は、土の中にしみこむ量よりもはるかに多く、約7割が地表を移動していると言われています。
水は高いところから低いところへと流れていきますので、くぼみがあればそこに溜まってしまいます。
まずはそのくぼみを土や砂利で埋めましょう。
広範囲にわたってびしょびしょになっているときは、雨水が敷地の外に出られずに溜まっている可能性があります。
案外、葉っぱや土がせきとめている場合がありますので、取り除いて水の流れをよくしましょう。
「傾斜をつける」のも効果的です。雨水の流れを敷地の外に誘導することで、水がたまらなくなります。
傾斜をつけるには、盛土の上に砂利を敷いたり、芝を張ったりするとよいでしょう。
水の流れをよくするもうひとつの方法は「穴を掘る」です。
庭に穴を掘ることで、自然と雨水が穴に向かって流れ込みます。
単に穴を掘っても多少の改善効果はありますが、傾斜をつけて掘った穴に雨水が向かうよう誘導するとなおよいでしょう。
ヤスデ対策その2「ヤスデが好みそうな場所をなくす」
「ヤスデが好みそうな場所をなくすこと」で、家の近くにヤスデがいない環境にしていきましょう。
ジメジメとした湿気の多い場所をなくすことが大切です。
まずは、家とその周辺の掃除からはじめましょう。

ヤスデが大好物な枯れ葉や腐葉土が溜まっている場所は取り除きましょう。
濡れたダンボールや、放置してある植木鉢とかありませんか?
家屋周辺にある雑草は除草しましょう。
ジメジメした環境は他のさまざまな害虫にとっても「住みやすい環境」ですので、ヤスデ以外の対策にもなりますので、徹底して対策をしていきましょう。
ヤスデ対策はいつしたらいいの?
ヤスデが1箇所に数十匹があつまっている光景のグロテスクさといったら半端ないです。
大量の卵から一斉に孵化をして、このような大量発生が起きていると思われる方も多いのではないでしょうか?
実はこのヤスデ、昨年の8月~9月に産み落とされたヤスデが成虫になったものなんです!
大量発生しているヤスデたちは、ずっと土の中に隠れていたということになります。
ヤスデは1匹あたり150~300の卵を産むという高い繁殖能力を持っています。
それに加えて、集団で行動する習性がありますので、なおさら大量に発生している感じがでているのではないでしょうか?
ちなみに1年通してのヤスデの活動スケジュールは下記のようになります。
ヤスデの活動スケジュールを
■ 8月~9月(産卵)
ヤスデは1回の産卵で300前後の卵を産むと言われています。
卵を産んだヤスデは死んでしまいます。
■ 9月~10月(秋雨、大量発生)
秋雨前線の停滞により長雨が続くと、ヤスデが土中から這い出してきます。
ただし、この時期のヤスデは産卵を終えて死んでしまっているため、梅雨の時期に比べると数は減ります。
■ 11月~4月(越冬)
気温が下がり、冬が始まると、落ち葉の下などで越冬をします。
脱皮を繰り返しながら徐々に大きくなっていきます。
この時期、ヤスデがいないように見えますが、実際は土の中に隠れているだけです。
■ 5月~7月(梅雨、大量発生)
梅雨の長雨の影響で、成虫になったヤスデが一斉に土壌表面に出てきます。
最も大量発生する時期です。
このように年に2回、ヤスデが大量発生する時期があります。
ヤスデが家に入ってこないようにするためには、最も大量発生する梅雨時期より前の「冬から春」に対策をとるのが効果的でしょう。
またヤスデの嫌がる成分の入った薬剤である「忌避剤」を家の外壁に沿って散布し、
家の周りを薬剤を囲い込んでヤスデを寄せ付けないようにするのよいでしょう。
まとめ
今回はヤスデがブロック塀や壁に大量発生しないための対策について紹介してみましたが、いかがだったでしょうか?
ヤスデ対策を簡単にまとめると、
・水はけをよくするために、雨水の流れを敷地の外に誘導する。(傾斜をつける、穴を掘る)
・ヤスデが好む環境を排除する。(エサとなる落ち葉や腐葉土を取り除くなど)
・ヤスデ対策は「冬から春」が効果的。
今回は、あくまでもヤスデを死滅させるための方法ではなく、家の周りに近づかせないようにするための方法についてまとめてみました。
ヤスデは確かに不快害虫ではありますが、土壌を改善してくれる「益虫」でもあります。
ヤスデが土からはいあがってこない対策をしておけば、植物の栄養源になる良質な肥料を得られるというメリットを受け続けることができます。(完全駆除してしまえばもちろんヤスデの恩恵は受けることはできません)
人間の都合で駆除するのではなく、共存していける対策をすることも必要なのではないでしょうか?
シロアリ駆除専門スタッフが
あなたのお悩みを解決いたします!!

- 羽アリが家から大量にでてきた
- 畳や床板など歩くとミシミシ音がするようになった
- 外壁や基礎部分にヒビや蟻道がある
- シロアリ保証期間が切れていた
- 脱衣所、洗面所などの床がブカブカする
- 家の周りや床下に木材(廃材)などを置いている
どのような疑問・質問にもすべてお応えします。
株式会社プログラントでは、現地調査点検・見積を無料で行っております。
まずはお気軽にご相談ください。
プログラントは安心と
信頼の5冠獲得





調査方法インターネット 調査
調査概要2022年2月 サイトのイメージ 調査
調査提供日本トレンドリサーチ
CONTACT
お問い合わせ
相談/見積り
完全無料
0120-778-114
24時間365日受付中

害獣・害虫・害鳥の スペシャリスト
藤井 靖光(Yasumitsu Fujii)
株式会社プログラント 代表取締役
拠点・連絡先
熊本本社
〒861-8002 熊本県熊本市北区弓削6丁目27-19
佐賀営業所
〒849-0937 佐賀県佐賀市鍋島3丁目9-5
お問い合わせ(代表)
緊急対応:7:00–22:00(年中無休/災害時は安全最優先の運用)
取扱分野
実績ハイライト
個人(藤井)調査実績
(1992–2025)
会社累計調査実績
(創業〜2025)
Google口コミ(熊本本社 334件)
Google口コミ(佐賀営業所 76件)
初回訪問スピード
最短当日訪問率 85%
報告書提出率
平均提出 10日
脚注:「個人=1992–現在」「会社=創業–現在(自社請負分)」
口コミ出典:Googleビジネスプロフィール[2025-08-12 時点]
定義:受付時間 7:00–16:00 の新規受付に対し 当日17:00までに訪問開始できた割合(警報発令・道路寸断日は母数除外)
主要資格・講習(抜粋)
- 建築物ねずみこん虫等防除業登録(熊本県)/熊市保30ね第1号
- 公益社団法人 日本しろあり対策協会/しろあり防除士[6名]/登録番号:13510
- 公益社団法人 日本しろあり対策協会/蟻害・腐朽検査士[2名]/登録番号:熊本県-17-0042
- 公益社団法人 日本木材保存協会/木材保存士[1名]
- 一般社団法人 住宅基礎コンクリート保存技術普及協会/住宅基礎コンクリート保存技術士[4名]/登録番号:J21-0211
- 一般社団法人 熊本県労働基準協会/特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者[2名]/登録番号:4350
- 高所作業車運転技能講習(コベルコ教習所)修了[4名]
- 一般社団法人 ペストコントロール技術者[1名]/登録番号:第2023-15号
- 公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター/防除作業監督者[1名]
- 狩猟免許(わな猟)[4名]/登録:P43-2019-N000460
ロープ高所作業(特別教育)について
当社はロープ高所作業(特別教育)修了者[4名]を配置。急勾配屋根・高所外壁・吹き抜けなどの高所作業において、事前リスクアセスメント/二重確保(バックアップ)/器具・アンカー点検/立入管理等の安全手順に基づき作業を実施します。
安全・法令・保証
法令遵守
鳥獣保護管理法/外来生物法/労働安全衛生法 等
賠償責任保険
あいおいニッセイ同和損保:対人/対物 各1億円(1事故あたり)
保証(要点)
対象・期間:
アライグマ/イタチ/ネズミ/シロアリ=5年、コウモリ=2年(※条件により最長10年)
適用条件:当社基準の封鎖+衛生施工を実施/(任意)年1回点検
除外:構造劣化・第三者工事・増改築・自然災害・餌付け 等
初動SLA:保証内再発のご連絡から 24時間以内に初動連絡/最短当日〜3日以内に訪問
安全実績
労災・薬剤インシデント 0件(直近36か月)
法令遵守:捕獲許可・鳥獣保護管理法 等の違反 0件(通算)
方針・運用ポリシー
方針:最新機材×従来機材/最新工法×従来工法/自社開発器具を融合したハイブリッド工法をケースに応じて最適化
施工記録の開示と保管・再発防止を徹底
編集・監修
「当サイトの技術記事は現場担当が執筆し、藤井 靖光が全件監修。公的資料・SDSを参照し、誤りは確認後速やかに訂正します。」
苦情対応
「受付 → 24時間以内に初動連絡 → 現地確認 → 是正 → 書面報告の順で対応します。」
安全・薬剤
「薬剤は用途・希釈・保管を社内SOPで管理。近隣・室内の隔離・換気・養生を徹底します。」
画像・記録の扱い
「施工写真・報告書は7年間保管。個人情報はマスキングのうえ事例公開します。」
会社FAQ
記事一覧へ