【結論】完全な害獣駆除はプロの業者でないと厳しい。

まず、このブログをお読みの方は、天井裏の害獣で悩みが多いことかと思います。
○突然の天井裏からの走る音・カリカリやゴトゴト・カサカサなどの音がする
○長年ダニに悩まされてきた
○壁の中や天井裏で鳴き声がする
○外で見かけた・家の中で見かけた
○自分で対策の仕方が分からない
○衛生面や配線など齧られないかが心配
○深夜から早朝の足音などで眠れない
などなど人によって悩みはさまざまです。
まず問合せの多くの方は、悩みを解決すべく、完全防除ではなく一時的な対処を行われています。
【一般的な対処とは?】
○ホームセンターで薬剤や罠・粘着シート・バルサンなど
○忌避スプレー等の購入
○バルサンを焚く・ショウノウを撒く
○光を点灯させる
○ネットで超音波機械や薬剤購入など
○大工や建築専門に見てもらって施工したけど?
○自分で害獣対策を色々としてきたけど音やニオイが止まらない・・・
○市役所などに電話したけど対応してくれない・・・・など
一時的に対処を施し、音や被害が少なくなったとしてもすぐに順応し慣れてしまいます。
また天井裏は梁や柱が入っており、そこを走っても下の部屋には響きません。
一旦害獣の巣と化した好環境の天井裏などでは簡単には離れてくれません。
「2~3日おきに走ったりするんだよね」と話されるのでカメラを仕掛けると梁や柱の上を走る姿が映ってるケースもあります。
つまり、天井板の薄い板を走るので下の部屋に響くわけです。
また、簡単なやり方では被害が元に戻る➡対処する➡元に戻る➡対処する➡元に戻る➡被害が拡大するのが現状です。
時間と労力とお金が無駄になってしまうケースがほとんどです。
大切な家を費用がかさまないようにと作業する気持ちもわかります。
でも、中途半端な対策は出費の無駄です。時間と大切なお金が費やされます。
また、ネット上で効果があると記述の超音波などは効きません。(訪問すると皆さん購入されてるんです)
施工をするとしても屋根上、屋根裏、床下へ入り、落下する・釘など刺さる危険性もあり、更には害獣に出会った場合は最悪噛みつかれるなどの危険もあります。
中々被害が止まらない・被害が拡大している・作業するのが面倒などの理由で弊社にご依頼を頂きます。
でもなるべくなら・・・業者に頼む前に何とかしたい・・・費用をかけたくない・・・
分かりました。
プロ直伝「誰でも簡単にできる害獣対策」とは?
最後まで熟読すれば駆除対策が丸わかりです。
天井裏に潜む害獣の特徴をまず知ろう(敵を知る)
この記事をご覧いただいている大半の方は、天井の走る音・齧る音・ガサガサゴトゴトなどの音が天井裏や壁の中から聞こえてきたり、天井裏のシミやニオイに悩まれたり、掃除や片づけなど清掃をしても痒いなど、どう対策を取るか悩まれていることと思います。
衛生面の心配をされる方も大半です。
本編では専門家・害獣駆除対策の専門としてアドバイス・害獣の特定から予防・対策に至るまで徹底解説をどこよりも深く分かりやすく説明していきますのでご覧下さい。

(解説)害獣の種類特定する事で、その害獣にあった対策方法が分かります。
害獣別に対策方法・駆除は全く違います。次の特徴を頭に入れてフンや足跡で害獣を見極めて下さい。
また良く点検してみると2種類・3種類の害獣の形跡が見つかるかもしれません。
イタチの糞があったけど、ネズミの糞もある場合は、ネズミは居ません。何故か?現在イタチが侵入している場合、警戒心の高いネズミは捕食される前に
逃げていってしまうからです。イタチ対策だけ施工で大丈夫?
いいえ。イタチが居なくなると賢いネズミは侵入してきます。封鎖する網もネズミサイズ(1㎝未満)なのです。
対策とすればイタチ・ネズミ両方の対策が必要となります。
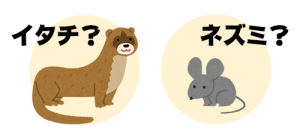
天井裏に潜む害獣の特徴・生態について 動物別危険度
イタチの特徴と生態について 危険度★★★☆☆
イタチは、日本全国に生息する哺乳類です。
イタチは通常、縄張りの中に家巣穴と休息用の巣穴を持っています。日中も外に姿を見せることがありますが、主に夜行性で、日が暮れると穴から出てきて活動します。糞や尿でコミュニケーションを図るのも特徴です。
人間の居住域の拡大に伴い、大都市圏や住宅地近くまで生息域を広げています。警戒心が強く、人目につくところに出てくることは稀ですが、ねぐらとエサを求めて家に入り込んできます。とくに寒くなる10月後半から入り込み3・4月は出産・5~8月までは子育てと天井裏ではイタチは一旦侵入すると中々出てはくれません。
《イタチの特徴》
○体型は、胴長・短足
○非常にすばしっこく動き回り、木や壁も垂直に登ることが出来、泳ぎも上手。
○頭が入ればどこでも侵入でき、わずか3cm(500円硬貨ほど)四方ほどの隙間があれば侵入してくると言われています。
○雑食性(ゴミや農作物も荒らす)ですが、肉食の傾向が強い(ネズミや鳥類、昆虫など)
○見た目が可愛いからと言って、絶対に触ったりしないように気をつけて下さい。自分から人に攻撃してくることはありませんが、触ると噛まれたり引っかかれたりする恐れがあります。
○追い詰める行為等、危険を感じると、肛門付近の臭腺から悪臭を放つ分泌液を出します。
○人に感染するマダニやノミなど寄生虫を保有している可能性があるので、素手では絶対に触らないで下さい。
○ヘビやハト、ネズミなどを巣穴(天井裏など)に運び込む。




アライグマの特徴と生態について 危険度★★★★★
アライグマは、北米原産で、道内にはペットとして輸入されましたが、気性が非常に荒いため、飼い主が捨てたり、脱走したりしたものが野生化し、天敵が居なく、繁殖能力が強いことなどの理由から、急速に生息範囲を全国的に拡大しています。
全国で、農作物被害が発生している他、民家に入り込み、糞尿などの大型害獣のため、場合により天井から落ちてくるの被害が深刻化したため、防除対象となる国の特定外来生物に指定されています。
見た目に反してどう猛で、近づくと噛まれる、ひっかくこともあり、人に感染する病気を保有していますので、目撃した際には絶対に近寄らないようにご注意下さい。


ネズミの特徴と生態について 危険度★★★★☆
日本におけるネズミは3種類。ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ
運動能力が高く、警戒心が非常に強く、学習能力がよくて賢い。一度学習すると罠でもかからないケースも多く手間がかかります。狭いところや物陰に沿って行動し、何でも齧る習性がある。簡易的な穴封鎖は効果が期待できない。雑食性で、肉類、穀類、野菜、果実など何でも食べるが、特に植物質を好む。
毒餌(殺鼠剤)がご飯代わりになるようなスーパーラットもいて、素人では駆除が難しい。また、ネズミは他の動物以上に色々な病原菌を持ち歩いているので衛生上気をつけなければならない生き物です。
ハクビシンの特徴と生態について 危険度★★★☆☆
ハクビシンは、沖縄を除く日本全域に生息し、体長は50~80cmで、10年ほど生きる。
冬眠はせず、繁殖力が旺盛。冬眠はせず、繁殖力が旺盛で、一年中子供を産むことができる。ハクビシンは雑食性で、植物や昆虫、他の動物など何でも食べる。甘いものが好きなようで、果物などの農産物をよく傷つけます。
ハクビシンは獰猛なので、見かけたら手は出さないで下さい。

コウモリの特徴と生態について 危険度★★☆☆☆
日本でよく見られるアブラコウモリは、体長4~6cm、体重10g程度の小さな生き物で、背中は灰褐色、腹部は灰色です。
コウモリは夜行性の動物で、夜になると天井裏など集団で眠り、日没頃になると空を飛びます。コウモリが最も活動的になる夏場の夕暮れ時に、空を飛ぶ姿がよく観察できます。コウモリによる最大の被害が糞尿による「悪臭」と「衛生的な被害」「環境被害」です。
コウモリは害獣よりかは益獣として捉えられています。毎日、身体の3分の1ほどの蚊や蛾などの昆虫を捕食し食べてくれるからです。
家の外周周りに同じところにフンが落ちている場合はコウモリの可能性が非常に高いです。5ミリの隙間があれば侵入してきます。
コウモリは冬には冬眠し春先から秋深まる頃まで1年を通すと活動期間が長いのでわずかな隙間さえも見逃すことなく防ぐことが重要です。
コウモリのフンの特徴は、様々な菌が含まれていることです。決して素手では触らないように注意して下さい。また、フンが乾燥すると、空気中に菌が舞い上がります。目には見えない空気に舞う粒子を吸い込んでしまうと感染症やアレルギーを発症し、衛生的な被害を出してしまうのです。


天井裏に住み着いた害獣の被害例
被害ケース①糞尿による被害
糞尿による被害で断熱材の効果はなくなります。また、天井板にはシミ…動物別では
○イタチの糞尿は「イタチの最後っ屁」の名の通り非常に臭いのが特徴でまとまってする特徴があります。
○アライグマの特徴では、人間と同サイズで大量に糞尿をすることで薄い天井などではかなりの被害が出ます。
○ネズミは、歩きながら・走って糞尿が出来、いたる場所で広範囲に被害が出るのが特徴です。
○コウモリは、出入り口に糞尿するケースが多いですが、壁の中などが多く、壁には糞尿でクロスにカビが生えます。
糞尿を薄い天井板の上で大量にされるとシミ・カビ・腐れの原因となり、場合によっては天井板の張替えが必要となるケースも見られます。
大きな個体や繁殖期は特に注意が必要で、短期間に木材の傷みが早くなります。
雨の日や梅雨時期になると部屋の中が臭くなるのが鬱陶しくなります。
被害ケース②断熱材損傷・ズレによる断熱効果の低減
天井裏の断熱材は、多くの害獣によって糞尿や断熱材を覆うビニールを破り断熱効果を半減・低下させます。
断熱材は本来、取替交換は不要な部材です。家の熱の出入りを断熱材が遮断してくれる大切な部材なのです。断熱材は、構造物の室内側と室外側を互いに断熱し、外から中へ熱が伝わるのを防ぐものです。熱伝導率の低い断熱材を使用し、すべてを密閉することが「夏涼しく、冬暖かい」住宅を目指します。
結露の発生も防ぐことが出来ます。
断熱材が害獣で損傷すると冷暖房効率が下がるだけでなく、内部結露で建築物が傷みやすくなるなどの弊害も起こります。害獣が踏み荒らして断熱材がズレることでも断熱効果が落ちますので気を付けましょう。

被害ケース③配線・ケーブル系の断線・漏電
天井裏には様々な電気の配線や太陽光の配線などがあります。天井裏に害獣が入り込むと配線関係を齧られる恐れがあります。齧られた配線に糞尿がかかる、埃がかぶると漏電の危険性があります。げっ歯類はなぜ齧るかというと、伸び続ける歯を削るためなのです。


被害ケース④騒音による被害
屋根裏に侵入する害獣の多くは夜から早朝にかけ行動します。毎晩・2~3日おき、中には日中まで活動する個体も居ます。走る音や鳴き声が壁の中や天井裏、ガサガサ・ゴトゴトすると僅かな音でも人によっては睡眠の邪魔をされ眠るのを妨げられます。
これが夜中になると気になって眠ることも出来ませんし、睡眠中でも目が覚めてしまいます。これが毎晩、2~3日おきに一回だとすると不安になり場合によってはノイローゼにもなりかねません。 睡眠は人間にとって重要な身体を休める時間ですので早めの対策は必要です。
その他の音の要因について
深夜から早朝にかけ活動する害獣はたとえ天井裏でなくても、瓦やスレート・ガルバなど材質によっては部屋内に音が振動で伝わり、もしかして?屋根の裏にいるのではないか?となるケースもあります。

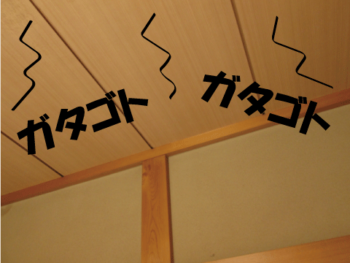
被害ケース⑤寄生しているダニ・ノミの被害(子供のアレルギーがひどくなる前に)
野生の生き物である害獣はすみかとなる天井裏と外を行き来します。そのため、体には色々なダニやノミが寄生・付着しています。寄生した状態で断熱材を巣にしているわけですから、ダニやノミが体から離れ断熱材が温床となります。 ダニやノミの大量発生・ダニやノミの死骸やフンなど吸い込んだり噛まれたりとしない前の対策が必要です。
天井裏は害獣の住みやすい環境だけではなくダニやノミにも住みやすい環境でもあるといえます。

被害ケース⑥病原菌や害虫が発生する(アトピー・喘息の要因)
ダニやノミ、病原菌や糞尿から害虫が発生すると、天井裏は環境的に悪化する一方で、ダニやノミの死骸やフンなど乾燥し、天井裏からの隙間や照明の隙間などから落ちてエアゾル感染することで、様々な感染症やアレルギー感染を引き起こす要因になりかねません。
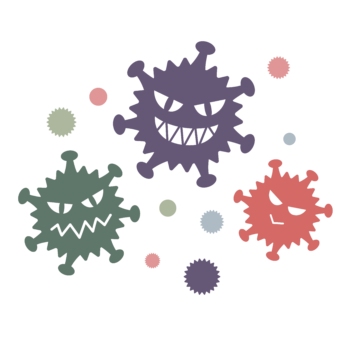

被害ケース⑦建物に被害が及ぶ・破損
天井裏に糞尿による腐れやカビ・シミ・天井板の張替えや配線や木材を齧る・断熱材の機能が失われる・臭く汚れる・アレルギーの原因となる等など、大事な住まいに害獣が入り込む上でのメリットは何一つありません。また修理にかかる費用もケースにより多額になる場合もあります。
被害ケース⑧経済的・時間的損失
天井裏害獣にかかる修理費用・また駆除を予防する大切な時間を損失します。しっかりと今後入らせない予防対策・駆除もしっかり対策しなければ2度手間、3度手間かかる場合があります。
自分で出来る・害獣特定する方法
天井裏を点検してみたい・どこから?必要な道具は?見るポイントとは?
天井裏入り口・ユニットバス入り口・床下収納庫・畳を開ける
天井裏の確認に必要なものは?(必ず2人以上で行うこと)
中々普段から入らない天井裏の環境は、年数とともに積もった埃や劣化した断熱材の飛散・天井の板には釘が貫いて刺さる危険性・下の階に足を踏み外して落下する危険性・電気配線に触れる、害獣がいる場合は乾燥したフンを吸い込むことも考えられる事から、最低2人以上連絡がとれる状態で万全な対策をしましょう。
【服装】
・簡易的な防塵マスク・ゴーグルなど
・手袋(手のひらがゴム製)
・ツナギ服(必要に応じて使い捨てできるもの)
・安全靴(釘などが刺さる危険性がある)
・帽子(釘などが刺さる危険性がある)
【作業用具】
・懐中電灯(ヘッドライト2つ以上)
・脚立(高さがある点検口の場合)
・カメラなど記録できるもの
・携帯もしくはトランシーバー
・足場板(天井を安全に作業するため)

初めて入るときは、天井の蓋で少し大きくドンドンと数回開け閉めして下さい。
数回で大丈夫です。(警戒心の高い害獣は突然の音で逃げる可能性が高いため)
【注意】害獣と遭遇した場合、害獣を幼獣であっても捕獲するのはやめてください。
もし、遭遇したらゆっくり退くのが良いでしょう。とっさに捕獲しようとすると、親に抵抗されて巻き込まれたり、噛みつかれたりすることがあります。
アライグマが噛む、コウモリのフンでのエアゾル感染での狂犬病を発症したら致死率100%です。(治す術が現在の医療ではありません。)
害獣であっても、子供を育てている動物は、身の危険を感じると恐怖を感じて攻撃態勢に入り襲われる危険性もありますので直接手を出すのは避けましょう。
天井裏に害獣が入ってくる要因とは?
①暖かい
②雨風をしのげる
③天敵が居ない
④虫が寄ってくるのでエサには困らない
天井裏は侵入する害獣にとっては最高の住処と言えます。1年を通すと雨風をしのぎ寒暖の差はありません。天敵も寄らない・巣としている断熱材があるという風に何をとっても住みよい環境なのです。
プロ直伝!徹底的な侵入口封鎖(今後の害獣具合が変わる)
①あきらめずに徹底的に屋根上から床下まで1cm以上の穴を調べ尽くす。
業者の無料調査を頼んでみても良いかもしれません。屋根なら屋根専門の業者に床下なら床下専門の業者に、害獣専門家の業者に数社無料調査してもらい、徹底的にネズミさえも通らない穴を調べてもらいましょう。
害獣の出入り口も見つけましょう。イタチの駆除だとした場合、イタチが居なくなるとネズミが侵入するケースが多いです。以前にネズミを見かけたなどあると今度はネズミに悩まされる危険性があるからです。イタチに合わせるのではなくネズミに合わせた施工を施すことで今後の心配はなくなります。
②害獣の出入り口とは?
害獣のよく出入りするところにはフンが落ちています。瓦には足跡がベッタリとつき、出入り口に羽が付着し汚れているのが侵入のサインであり害獣の出入り口なのです。追い出しを図る際の最後の閉じる穴となりますので注意して確認して下さい。
③大きな穴などは大工に頼むのがベスト!(2段構え封じ)
大工は木工事のプロです。大きな穴や割れ・外れかかる穴など、隙間なく塞いでくれます。塞いだ上で、屋根上の隙間なら漆喰などで更に上塗りして固めましょう!
④風の通る通気口などは錆びないステンレス等で、通気が必要ない穴は2段構え封じで。通気口工法の新築の家は通気口には虫が入らないようにステンレスの防虫網が施されています。通気を確保しつつ、ガッチリと固定していきましょう。網はステンレスで固定はコーキングがベスト!


(床下通気口のステンレス網の取り付け)


(どんな場所の封鎖にも完全に封鎖)
⑤害獣の侵入口を1~2箇所残し侵入漏れが無いように徹底的な封鎖。
害獣の侵入口を残すにはわけがあります。逃げ道を残しておくことで追い出しをスムーズにするためです。
⑥再度、害獣の侵入口の漏れがないかの確認
害獣の侵入口漏れがあると再発のリスクが高くなります。何度も見返し、封鎖の甘さがあるところはガッチリと固定して下さい。
⑦害獣追い出し開始!(バルサンや忌避スプレーなど使い追い出しましょう)
バルサンや忌避スプレーなどで追い出しを図りましょう。また、バルサン等は投げ込まず、断熱材などを避けるか、どかして置くように設置して下さい。
⑧害獣の音や気配ないかの確認
1日~2日様子を確認してみます。
⑨まだ天井裏にいそうな場合は追い出しを繰り返す(⑦~⑧繰り返し)
⑩害獣の出入り口は念入りに調べて最後に出入り口を閉じる。
⑪閉じ込めた場合もあった場合、ここで箱罠を仕掛ける。
秘訣 害獣追い出しの確実性を増す方法があります!
それはなにか?巣をなくすことです。追い出しをする前にすべての断熱材(壁以外)を剥ぐのが効果的です。
この機会に断熱材の種類の検討をしても良いのかもしれません。害獣は断熱材を巣にするケースが大半で、イタチ・アライグマは袋を破り断熱材を巣とします。
一方、ネズミは断熱材の下に潜伏するケースが多くフンが断熱材を剥ぐとよく見られます。
つまり、1階・2階の断熱材を剥いでない状態にして追い出しすれば効果が倍増します。害獣の巣と化した断熱材はフンや尿・ダニやノミの温床となるので最後に新しいものに交換下さい。
プロ(弊社)の害獣追い出しはココが違う!
弊社では追い出し業務用薬剤(忌避剤を動物ごと)に切り分けます。
追い出し効果は、市販剤と比べ業務用薬剤がはるかに効果があり、安全性が高い薬剤を業務用機器で効率よく隅々にいたるまで行き渡らせ追い出しを徹底的に図ります。
また、機器には燻煙タイプとULV(特徴は短時間の処理で高濃度の薬液が空中に漂うことによって隅々まで薬剤が浸透し、駆除に極めて有効で作業能率も上がります)を使用します。
小さなお子様がご在宅の場合は薬剤を使わない、弊社独自の開発機器で追い出しを図る方法と弊社独自の開発機材で一段効果が高いレベルでの追い払いも可能です。
断熱材は家にとって重要な部材です。冬は熱を逃さず、夏は涼しくしてくれます。市場にはさまざまな種類の断熱材があるので、ニーズにあったものを選ぶことが重要です。ガラス繊維の断熱材は、断熱材の最も一般的な種類の一つであり、リサイクルされたガラスから作られています。専門家に依頼することも、自分で施工することも可能です。
天井裏害獣の解決まであと一歩…。侵入口も全て塞いだ・箱罠にもかかりなし・足音も気配がないとくれば…。
天井裏の清掃と消毒作業と断熱材の敷き込みで終わりとなります。
まずは小型のほうきとちりとりとゴミ袋を用意しましょう。
断熱材撤去の際の断熱材やフンや木切れなどたくさんあるかと思います。
今後清掃する機会がないかと思いますので丁寧に清掃するのが大切です。
天井裏の清掃お疲れ様です。
天井裏のダニ・ノミの対策です。
ここはバルサンで一気に焚きましょう。バルサンの投げ込みは厳禁です。すぐには煙など出ませんのでゆっくり設置しましょう。1日バルサンを放置した後、次の工程に入ります。
消毒作業(フンやウイルス対策)
断熱材を敷く前に、ダニ駆除のバルサンを焚いて1日経ったら糞を掃除する。この時、スプレータイプの噴霧器で隅々まで消毒します。

断熱材の敷き込み
この時点で最後のひと押しが必要です。グラスウール断熱材を穴があかないように丁寧に敷き詰めて下さい。隙間があると熱が出たり入ったりして、断熱性が損なわれてしまうので、じっくりと敷き詰めて下さい。
【よくあるご質問】
①質問 秋から春まで天井を不明な動物がうるさかったけど夏はいないのは何故?
答え 害獣は秋深まる頃(稲刈りが終えた)から天井裏へ侵入してきます。そこから3~4月の暖かくなるころに出産シーズンに入り7月まで子育てと長いシーズン天井裏へ 侵入します。特に子供が生まれてから活発に盛んになってきます。被害が酷くなるのはこの頃からで、夏場は天井裏の温度の上昇・餌が豊富な場所へ移動する為なのです。
でも家の立地条件や周囲の環境次第では年中侵入しているケースもあります。

②質問 通販での撃退マシーンや超音波などの機械を購入しようか迷っているのですが。
答え 期待されるほどの効果はあまり望まないのが得策です。 一時的に効果があったとしても順応し効果が無くなってきます。基本的なことは徹底的に追い出し、ネズミも 入らない施工を目指す事。 家は古い・穴だらけの家もあります。専門家は屋根の上から床下まで1つずつ確実に再発しないよう全ての穴を封鎖し再侵入させない施工を目指します 基本的なことなのですが一番重要なのです。
また中に閉じ込めた害獣も専門的手法で確実に仕留めます。
③どういった施工をされるのですか?
答え 害獣によって対策方法は違います。 効率よく「今天井裏にいる害獣を追い出し、今後一切再侵入させない屋根上から床下までの徹底的な封鎖を目指し、動物が居なかった時の状況に戻す」施工を行っております。侵入口封鎖に関しては家の換気は大切です。 ステンレス網などを使用し強力固定で通気も妨げないよう、また通気する場所でない箇所は状況に応じて完全固定・剥がれない施工をしていきます。

まとめ~プロの業者に依頼しましょう~
天井裏の害獣駆除・対策いかがだったでしょうか?
中々一般の方では効率・危険性・確実さなど考えると簡単にはいかないのはお分かりいただけたと思います。
弊社ではここでは語れないプロの匠の技・弊社独自の駆除技術・撃退機器・もっと効率の良い施工方法などたくさんあります。
また、色々な現場を柔軟に対応できる資格保有・経験豊富なスタッフが再発しない施工・お客様に喜ばれる施工を日々研究・打ち合わせしながら頑張っています!
弊社では他所に断られた施工・他所でしたけど再発して止まらない・安心してお仕事をお願いしたいなどのお客様は、まず弊社の無料お見積もり・無料調査をお受け下さい。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。
シロアリ駆除専門スタッフが
あなたのお悩みを解決いたします!!

- 羽アリが家から大量にでてきた
- 畳や床板など歩くとミシミシ音がするようになった
- 外壁や基礎部分にヒビや蟻道がある
- シロアリ保証期間が切れていた
- 脱衣所、洗面所などの床がブカブカする
- 家の周りや床下に木材(廃材)などを置いている
どのような疑問・質問にもすべてお応えします。
株式会社プログラントでは、現地調査点検・見積を無料で行っております。
まずはお気軽にご相談ください。
プログラントは安心と
信頼の5冠獲得





調査方法インターネット 調査
調査概要2022年2月 サイトのイメージ 調査
調査提供日本トレンドリサーチ
CONTACT
お問い合わせ
相談/見積り
完全無料
0120-778-114
24時間365日受付中

害獣・害虫・害鳥の スペシャリスト
藤井 靖光(Yasumitsu Fujii)
株式会社プログラント 代表取締役
拠点・連絡先
熊本本社
〒861-8002 熊本県熊本市北区弓削6丁目27-19
佐賀営業所
〒849-0937 佐賀県佐賀市鍋島3丁目9-5
お問い合わせ(代表)
緊急対応:7:00–22:00(年中無休/災害時は安全最優先の運用)
取扱分野
実績ハイライト
個人(藤井)調査実績
(1992–2025)
会社累計調査実績
(創業〜2025)
Google口コミ(熊本本社 334件)
Google口コミ(佐賀営業所 76件)
初回訪問スピード
最短当日訪問率 85%
報告書提出率
平均提出 10日
脚注:「個人=1992–現在」「会社=創業–現在(自社請負分)」
口コミ出典:Googleビジネスプロフィール[2025-08-12 時点]
定義:受付時間 7:00–16:00 の新規受付に対し 当日17:00までに訪問開始できた割合(警報発令・道路寸断日は母数除外)
主要資格・講習(抜粋)
- 建築物ねずみこん虫等防除業登録(熊本県)/熊市保30ね第1号
- 公益社団法人 日本しろあり対策協会/しろあり防除士[6名]/登録番号:13510
- 公益社団法人 日本しろあり対策協会/蟻害・腐朽検査士[2名]/登録番号:熊本県-17-0042
- 公益社団法人 日本木材保存協会/木材保存士[1名]
- 一般社団法人 住宅基礎コンクリート保存技術普及協会/住宅基礎コンクリート保存技術士[4名]/登録番号:J21-0211
- 一般社団法人 熊本県労働基準協会/特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者[2名]/登録番号:4350
- 高所作業車運転技能講習(コベルコ教習所)修了[4名]
- 一般社団法人 ペストコントロール技術者[1名]/登録番号:第2023-15号
- 公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター/防除作業監督者[1名]
- 狩猟免許(わな猟)[4名]/登録:P43-2019-N000460
ロープ高所作業(特別教育)について
当社はロープ高所作業(特別教育)修了者[4名]を配置。急勾配屋根・高所外壁・吹き抜けなどの高所作業において、事前リスクアセスメント/二重確保(バックアップ)/器具・アンカー点検/立入管理等の安全手順に基づき作業を実施します。
安全・法令・保証
法令遵守
鳥獣保護管理法/外来生物法/労働安全衛生法 等
賠償責任保険
あいおいニッセイ同和損保:対人/対物 各1億円(1事故あたり)
保証(要点)
対象・期間:
アライグマ/イタチ/ネズミ/シロアリ=5年、コウモリ=2年(※条件により最長10年)
適用条件:当社基準の封鎖+衛生施工を実施/(任意)年1回点検
除外:構造劣化・第三者工事・増改築・自然災害・餌付け 等
初動SLA:保証内再発のご連絡から 24時間以内に初動連絡/最短当日〜3日以内に訪問
安全実績
労災・薬剤インシデント 0件(直近36か月)
法令遵守:捕獲許可・鳥獣保護管理法 等の違反 0件(通算)
方針・運用ポリシー
方針:最新機材×従来機材/最新工法×従来工法/自社開発器具を融合したハイブリッド工法をケースに応じて最適化
施工記録の開示と保管・再発防止を徹底
編集・監修
「当サイトの技術記事は現場担当が執筆し、藤井 靖光が全件監修。公的資料・SDSを参照し、誤りは確認後速やかに訂正します。」
苦情対応
「受付 → 24時間以内に初動連絡 → 現地確認 → 是正 → 書面報告の順で対応します。」
安全・薬剤
「薬剤は用途・希釈・保管を社内SOPで管理。近隣・室内の隔離・換気・養生を徹底します。」
画像・記録の扱い
「施工写真・報告書は7年間保管。個人情報はマスキングのうえ事例公開します。」
会社FAQ
記事一覧へ
関連記事
2025.09.19
福岡県みやま市 コウモリ駆除5冠達成! お客様喜びの声 プログラント
ネズミ地域別害獣駆除2025.08.23
熊本県熊本市 ネズミ駆除5冠達成! お客様喜びの声 プログラント
イタチ地域別害獣駆除2025.08.01
福岡県大刀洗町 イタチ駆除5冠達成! お客様喜びの声 プログラント
地域別害獣駆除2023.10.02
熊本県 熊本市南区野口 コウモリ駆除5冠達成!
イタチ地域別害獣駆除2025.08.12
熊本県玉名郡玉東町 イタチ駆除5冠達成! お客様喜びの声 プログラント
アライグマイタチコウモリネズミ地域別害獣駆除2025.11.19
屋根裏の異変や音「荒尾市 害獣駆除」地元業者の弊社にお任せ!


















