
様々な被害を生む害獣のイタチ。
可愛らしい顔とは反してものすごく狂暴な生き物です。
時には、人をも襲ってくることがあります。
そんな多くの被害を生み出すイタチですが、駆除を行うには資格や許可が必要なのをご存知でしたか?
害獣による被害で最も多いのは、農作物の荒らしです。個人の家を汚染し、そこに住む人の健康被害を引き起こす可能性があるので、見つけたらできるだけ早く処分することを心がけたいものです。
ただし、むやみに害獣を駆除したり、捕獲したりすることは法律違反となります。
害獣なのに、なぜ駆除してはいけないのでしょうか?
日本にいる生物達は”鳥獣保護法によって守られているから”です。
鳥獣保護法は、動物の捕獲や殺生を差別なく防止し、生物多様性を保全しようとするものです。
したがって、無許可の捕獲や駆除は犯罪となります。
市から許可を得ていても、わなや道具を使って罠を仕掛ける場合は狩猟免許が必要です。
無資格者が許可なく害獣駆除を行うと、鳥獣保護法違反となります。罰則が適用される場合があります。
鳥獣保護法では、法律で認められていない動物を捕獲した場合、100万円以下の罰金または1年以下の懲役と定められています。
また、捕獲が許可されていても、捕獲許可証を持参していない場合は30万円以下の罰金となりますので、ご注意ください。
非常に重要なポイントとなりますので、押さえておきましょう。
イタチ駆除にはどんな資格が必須なのか、また、免許の取得の仕方から注意したいことまで解説していきます。
最後まで熟読よろしくお願いします。

イタチ駆除には資格が必要!

冒頭でも申し上げたように、日本国内でイタチの駆除をするには、まず自治体の許可が必須になります。
駆除方法の中でも罠による捕獲や、網による捕獲、銃等による捕獲には狩猟免許が必要になってきます。
罠も、わな猟免許が必要になってきます。
忌避剤を使用しての追い出しには免許は不要です。
しかし、イタチも学習するため、忌避剤もずっと有効ではありません。
例えば、忌避方法として光や音を使用した忌避方法がありますが、イタチはすぐに慣れてしまいます。
害獣だけど勝手に駆除してはダメ!

害獣に分類される動物は、人に危害を加える可能性があります。
必ずしも被害が出るとは限りませんが、有害と判断された場合以外は駆除できません。
もし見つけても、手を出さないようにしましょう。
たとえ危害を加えられたとしても、やむを得ない場合を除き、殺してはなりません。
罠や捕獲の免許をお持ちの方は、害獣が傷つかない罠を選んでください。
また、捕まえた害獣は、放獣して下さい。
一部のネズミ以外の害獣は許可が必要!鳥獣保護管理法について

章題の通りですが、一部のネズミ以外の害獣の駆除には許可が必要になってきます。
害獣と呼ばれる生き物で、我が国で被害が多くみられるのは、ネズミ・イタチ・アライグマ・ハクビシン・イタチ・コウモリなどです。
上記は一部です。害獣と呼ばれる動物ですが、”鳥獣保護法 “の対象になっています。
人間にとっては害獣といえども、むやみやたらと害獣を捕獲したり駆除をしてしまうと、生態系が崩れる原因となってしまうので、自然の恩恵を受けることができなくなってしまいます。
それを防ぐためにも、害獣駆除には資格や許可が必要になったりするのです。
例外で、ネズミは環境衛生への影響が大きいので、資格や許可がなくても駆除することが可能です。
イタチ駆除に必要な資格
![]()
イタチを駆除するには資格や許可が必要ということは解説してきました。
では具体的にどのような資格があるのでしょうか。見ていきましょう。
防除作業監督者
防除作業監督者は、構造物の衛生的な環境を確保するために、ねずみや昆虫の駆除に必要な知識と能力を有していることを証明する国家資格です。
|
受講日程 |
各都道府県による |
| 試験方法 | 講習 |
| 受験資格 | 1)学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令36号)に基づく中等学校を卒業した後、2年以上建築物におけるねずみ、昆虫等の防除(シロアリ駆除を除く)に関する実務に従事した経験を有する者 2)5年以上建築物におけるねずみ、昆虫等の防除(シロアリ駆除を除く)に関する実務に従事した経験を有する者 3)①と同等以上の学歴及び実務の経験を有すると認められる者 (1〜3のいずれかに該当する者) |
| 受講料 | 60,000円 |
| 受講場所 | 東京・大阪・福岡など |
狩猟免許
狩猟技術ごとに、散弾銃・小銃の第一種銃猟免許、空気銃の第二種銃猟免許、わな猟免許、網猟免許の4種類があります。
毎年、狩猟免許の種類ごとに、各都道府県で複数回の試験が行われています。
受験を希望される方は、日時や場所などの詳細について、各都道府県の担当部署に直接お越しいただくか、お問い合わせください。
ペストコントロール技術者
ペストコントロール(有害生物の防除)を行う技術を有する者に与えられる専門資格。
1~3級、名誉技術者の4つの区分があります。
ペストコントロール技能士
効果的な調査を行うには、対象となる生物の生態を理解するだけでなく、どのような法律や規制が適用されるかを知っている必要があります。
これらをマスターした証として「ペストコントロール技能師」の資格が授与されます。
害獣駆除を資格や許可なく行ってはいけない理由

野生動物をむやみに保護したり、殺したりすることは「鳥獣保護管理法」で禁止されています。
そのため、駆除する害獣によっては資格や許可が必要です。
無資格・無許可での動物の駆除は鳥獣保護法違反となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となりますので、ご注意ください。
イタチ駆除は専門の業者に依頼を!
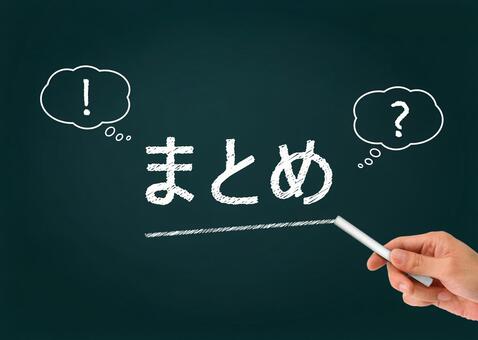
イタチ駆除には資格や許可がいることはお分かりになられたと思います。
鳥獣保護管理法で保護されているイタチの狩猟には免許が必要です。
そのため、専門家でない者が無許可でイタチを狩猟・駆除することは違法とされていることも分かられたと思います。
イタチ駆除には資格や許可のみならず、確かな知識と豊富な経験、技術が必要になってきます。
そのため、イタチを自分で駆除するのはかなりハードルが高いです。
だからといって、イタチを放置することはできません。
放置すればどんどん被害は増すばかりです。
ですので、決してイタチは放置してはなりません。
あらゆる被害を産みますので、イタチがいるかもしれないと思ったら直ちに専門の駆除業者へ連絡しましょう。
株式会社プログラントではイタチの現地調査からお見積りまでは無料にて行っております。
また、九州北部エリアのシロアリ・害獣駆除業者で初の5冠を獲得いたしました。
Googleクチコミ★★★★★(4.8/5.0)という高い評価を頂いております。
顧客満足度調査97.5%(2021年自社調べ)のご支持を頂いております。
安心してご依頼下さい。
まずはお気軽にお電話からご相談をお待ち申し上げております。
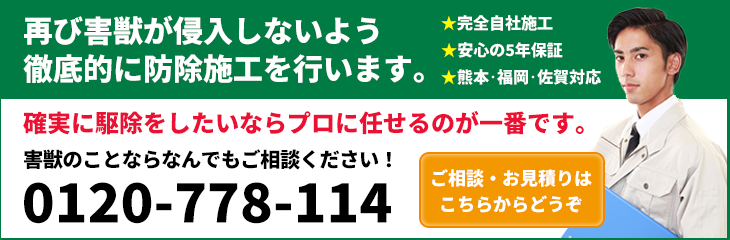
シロアリ駆除専門スタッフが
あなたのお悩みを解決いたします!!

- 羽アリが家から大量にでてきた
- 畳や床板など歩くとミシミシ音がするようになった
- 外壁や基礎部分にヒビや蟻道がある
- シロアリ保証期間が切れていた
- 脱衣所、洗面所などの床がブカブカする
- 家の周りや床下に木材(廃材)などを置いている
どのような疑問・質問にもすべてお応えします。
株式会社プログラントでは、現地調査点検・見積を無料で行っております。
まずはお気軽にご相談ください。
プログラントは安心と
信頼の5冠獲得





調査方法インターネット 調査
調査概要2022年2月 サイトのイメージ 調査
調査提供日本トレンドリサーチ
CONTACT
お問い合わせ
相談/見積り
完全無料
0120-778-114
24時間365日受付中

害獣・害虫・害鳥の スペシャリスト
藤井 靖光(Yasumitsu Fujii)
株式会社プログラント 代表取締役
拠点・連絡先
熊本本社
〒861-8002 熊本県熊本市北区弓削6丁目27-19
佐賀営業所
〒849-0937 佐賀県佐賀市鍋島3丁目9-5
お問い合わせ(代表)
緊急対応:7:00–22:00(年中無休/災害時は安全最優先の運用)
取扱分野
実績ハイライト
個人(藤井)調査実績
(1992–2025)
会社累計調査実績
(創業〜2025)
Google口コミ(熊本本社 334件)
Google口コミ(佐賀営業所 76件)
初回訪問スピード
最短当日訪問率 85%
報告書提出率
平均提出 10日
脚注:「個人=1992–現在」「会社=創業–現在(自社請負分)」
口コミ出典:Googleビジネスプロフィール[2025-08-12 時点]
定義:受付時間 7:00–16:00 の新規受付に対し 当日17:00までに訪問開始できた割合(警報発令・道路寸断日は母数除外)
主要資格・講習(抜粋)
- 建築物ねずみこん虫等防除業登録(熊本県)/熊市保30ね第1号
- 公益社団法人 日本しろあり対策協会/しろあり防除士[6名]/登録番号:13510
- 公益社団法人 日本しろあり対策協会/蟻害・腐朽検査士[2名]/登録番号:熊本県-17-0042
- 公益社団法人 日本木材保存協会/木材保存士[1名]
- 一般社団法人 住宅基礎コンクリート保存技術普及協会/住宅基礎コンクリート保存技術士[4名]/登録番号:J21-0211
- 一般社団法人 熊本県労働基準協会/特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者[2名]/登録番号:4350
- 高所作業車運転技能講習(コベルコ教習所)修了[4名]
- 一般社団法人 ペストコントロール技術者[1名]/登録番号:第2023-15号
- 公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター/防除作業監督者[1名]
- 狩猟免許(わな猟)[4名]/登録:P43-2019-N000460
ロープ高所作業(特別教育)について
当社はロープ高所作業(特別教育)修了者[4名]を配置。急勾配屋根・高所外壁・吹き抜けなどの高所作業において、事前リスクアセスメント/二重確保(バックアップ)/器具・アンカー点検/立入管理等の安全手順に基づき作業を実施します。
安全・法令・保証
法令遵守
鳥獣保護管理法/外来生物法/労働安全衛生法 等
賠償責任保険
あいおいニッセイ同和損保:対人/対物 各1億円(1事故あたり)
保証(要点)
対象・期間:
アライグマ/イタチ/ネズミ/シロアリ=5年、コウモリ=2年(※条件により最長10年)
適用条件:当社基準の封鎖+衛生施工を実施/(任意)年1回点検
除外:構造劣化・第三者工事・増改築・自然災害・餌付け 等
初動SLA:保証内再発のご連絡から 24時間以内に初動連絡/最短当日〜3日以内に訪問
安全実績
労災・薬剤インシデント 0件(直近36か月)
法令遵守:捕獲許可・鳥獣保護管理法 等の違反 0件(通算)
方針・運用ポリシー
方針:最新機材×従来機材/最新工法×従来工法/自社開発器具を融合したハイブリッド工法をケースに応じて最適化
施工記録の開示と保管・再発防止を徹底
編集・監修
「当サイトの技術記事は現場担当が執筆し、藤井 靖光が全件監修。公的資料・SDSを参照し、誤りは確認後速やかに訂正します。」
苦情対応
「受付 → 24時間以内に初動連絡 → 現地確認 → 是正 → 書面報告の順で対応します。」
安全・薬剤
「薬剤は用途・希釈・保管を社内SOPで管理。近隣・室内の隔離・換気・養生を徹底します。」
画像・記録の扱い
「施工写真・報告書は7年間保管。個人情報はマスキングのうえ事例公開します。」
会社FAQ
記事一覧へ
関連記事
2025.08.01
佐賀県鳥栖市 イタチ駆除5冠達成! お客様喜びの声 プログラント
アライグマイタチコウモリネズミ地域別害獣駆除2025.10.19
「太宰府市 害獣駆除」“今すぐ何とかしたい”方へ:相談→調査→封鎖の最短ルート
アライグマイタチコウモリネズミ地域別害獣駆除2025.11.19
家屋へ害獣の侵入「天草市 害獣駆除」地元業者にお任せください
イタチ2023.10.07
ニホンイタチの生態とその分布について
イタチ地域別害獣駆除2025.08.12
熊本県宇城市 イタチ駆除5冠達成! お客様喜びの声 プログラント
イタチ2025.04.18
3分で納得!イタチの習性と特徴 2025年最新版


















