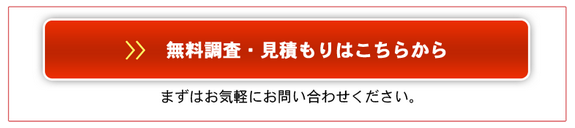アシナガバチはスズメバチ科のハチなので一見スズメバチに似た見た目をしていますが、
名前の通りスラリと伸びた長い足が特徴のハチです。
夏から秋にかけてスズメバチとともに、アシナガバチの巣の駆除の依頼もよく受けます。
ではそれ以外の季節のアシナガバチはどう過ごしているのでしょうか?
この記事ではアシナガバチの巣の特徴と、1年の様子、
季節ごとの駆除方法や注意点についてお伝えしていこうと思います。
アシナガバチの巣の特徴
アシナガバチとスズメバチは似たような黄色(もしくはだいだい色)と黒の似たような模様で、
足の長さ以外の違いがわかりにくいかと思います。
ですがその「巣」の形は大きく違います。
スズメバチが一般的にハチの巣でイメージされる、ボール状でマーブル模様の巣であるのに対し、
アシナガバチは幼虫を育てる六角形の穴が外に露出しており、以下の写真のようなシャワーヘッド状の形をしています。

巣の材料は樹皮や草です。
春になると冬眠から目覚めたアシナガバチの女王は
木などを少しずつ鋭いアゴでかじり取ってひとまとめにします。
更に噛み続け、その繊維のかたまりはドロドロになります。
噛み続けるうちにアシナガバチの女王の唾液と混じり、
より丈夫で強い巣の材料になります。
アシナガバチの巣は、和紙のようなものでもあります。
紙と同じような材料で出来た丈夫な巣です。
女王蜂は、巣の材料のかたまりをくわえ、巣を作る場所へ持っていきます。
これから大きくする巣の為に、巣の柄の部分を念入りに作り出します。
かたくて丈夫な巣を支える柄が出来上がったら、柄の下に部屋を作ります。
薄くのばして筒形の形にし、乾くと薄い紙の壁で出来た部屋になります。
ハチの巣のあのキレイな六角形は、大顎をコテのようにして材料をのばしたり、
触覚を定規代わりに使いながら出来上がります。
女王蜂は何度も何度も材料を運んで巣を作り、
巣が出来上がると卵を産み、働き蜂を育てます。
巣を守るために
アシナガバチの女王は、自分のお腹の部分から巣を狙う
「アリ」が嫌う物質を出すことが出来ます。
巣の付け根の部分にこの物質を塗り付けておけば
巣作りの最中でも、留守の間アリが近付くことが出来ないようにします。
女王が出すこの物質は、長い間効き目があるわけではないので
何らかの理由で女王の帰りが遅くなれば、巣はアリに襲われてしまいます。
アシナガバチの1年
ではこの記事の主題の一つでもある、アシナガバチの一年の様子を見てみましょう。
◆春

越冬し目覚めた女王蜂は1匹で枯れた木や草の繊維を使って巣作りを開始します。
部屋が出来るとひとつ卵を産み、また部屋を作ると卵を産み、
卵を産んで子育てを始めた女王蜂は、自分のエサを食べに行く時と、
巣の材料を取りに行く以外、巣のそばを離れずずっと巣を守ります。
この頃のアシナガバチの卵は、まだ気温が低いため孵化するまでに3週間程かかり、
その間、女王蜂は巣作りと卵を産むことに専念しています。
女王蜂は、幼虫が孵化しだすと子ども達にエサを与えます。
アシナガバチの幼虫のエサは、蝶や蛾の幼虫を肉団子にしたものです。
女王蜂は、獲物を見つけると飛びつき、大きな顎で噛み殺します。
子ども達が食べられそうな柔らかい部分だけで肉団子を作り
肉汁は一旦自分の胃にため込み肉団子と一緒に巣に持ち帰ります。
女王蜂はひとつづつ幼虫の部屋をまわり、肉団子をかじり取らせます。
肉団子を配り終わると、胃の中にためていた肉汁を口移しで与えます。
この時女王蜂は、子ども達から糖分を含んだ唾液をもらいます。
この頃の女王は一日に何度も肉団子を運んでは幼虫に与え、
大きくなってきた幼虫に合わせて巣も大きくしなくてはいけません。
狩りをして幼虫にエサを与えたり、巣の材料を運んだりとても忙しい時期です。
◆夏
そして幼虫は成長すると、部屋の入り口にカイコのように口から糸を吐きフタをします。
フタをした幼虫たちは部屋の中で蛹(さなぎ)になり、6月頃には繭(まゆ)を破って働き蜂が誕生します。
生まれた蜂たちは全てメスで、このまま巣に残り、女王の手伝いをする働き蜂となります。
そのうち、狩りや幼虫の世話、巣作りまでこなすようになり、
女王蜂は産卵に集中できるようになります。
7月から8月頃にかけて、働き蜂による巣づくり・エサ捕り・幼虫の世話など活動が本格化し、
女王蜂が卵を産みどんどん巣が大きくなる頃です。
もともと大人しいアシナガバチも、この頃は少し攻撃性が増してくる時期でもあり、
アシナガバチの被害報告も増えてくる季節になります。
◆晩夏~秋
8月後半になると雄蜂が羽化しだし、やがて翌年女王となる新しい女王蜂も誕生します。
9月頃には巣や木の枝に群がり、じっとしていることが多くなります。
10月頃にはオスバチが飛び回り、新しい女王蜂と交尾をします。
◆晩秋~冬
11月初め~半ば頃には次期女王蜂を残し、全ての蜂は死んでしまいます。
アシナガバチの巣は来年も使われるということはありません。
新しい女王蜂は、寒さをしのぐため木の隙間や石の陰に隠れ、じっと春を待ちます。
時期ごとのアシナガバチの駆除方法
このように季節ごとに異なる活動をしているアシナガバチですが、
家の敷地や人の通る場所に巣を作っている場合、刺される危険性がありますので、
駆除の必要が出てくると思います。
季節ごとにアシナガバチの危険性や駆除の方法が異なってきますので、
以下で説明していきたいと思います。
●春
女王バチが一匹で巣作りしている時の、
初期の巣の場合は、一番駆除がしやすい時期です。
まだ働き蜂も生まれてなく、一匹でいる場合は、巣を刺激して
落としてしまっても女王バチは攻撃してくることはありません。
ただ、巣を取ったとしても同じ場所に繰り返し巣を作り直す習性があるので、
再び巣を作らないよう、スプレー式の殺虫剤を噴射して、予防しておきましょう。
ハチは殺虫剤に弱いので薬剤をスプレーするのは有効的です。
●夏(6月頃)
働き蜂が生まれてきている場合、巣の様子をしっかり観察しておきましょう。
ハチは夕方頃になると、巣に戻って休みます。
活動が弱まっている夕方から朝方にかけての駆除が一番安全です。
夜間の場合は懐中電灯など使用すると思いますが、
蜂が懐中電灯の灯りにむかって飛んでくることがあるので
赤いセロファンなどをかぶせるようにして下さい。
夜間は周囲が暗くてよく見えないため、慣れていない方にはオススメできません。
駆除したあと巣を取り除いて、戻ってきたハチが巣を探して
辺りを飛び回りますが、攻撃してくる可能性は低いです。
巣があった場所辺りに、殺虫剤をスプレーしておくと
巣にいなかった戻り蜂はその時、薬剤に触れると死んでしまいます。
●夏(7月~9月頃)
7月初旬から9月下旬位はアシナガバチの活動が最も盛んになります。
基本的には巣に近づくことがなければ危険はないのですが、
アシナガバチも巣を守るのに必死です。
迂闊に近づいてしまえば、被害が出てしまう恐れもあるため、
危険な場所に巣がある場合は、早めの駆除が必要です。
ハチの巣が最盛期の場合は、アシナガバチも攻撃的になり、
個人で駆除を行うには危険が伴います。
できればハチ駆除専門業者による駆除をオススメします。
夏から秋にかけては、子育て等もあり活動が活発になりますので、
庭木のお手入れや、アウトドアで山や自然の豊富な場所にお出かけの際には、
周りにハチがいないか十分気を付けて下さい。
蜂に刺された場合は、様子をみてしっかりと処置を行い、
心配であったり、重症の場合はすぐに医療機関に受診するようにしましょう。
まとめ~最盛期のアシナガバチの駆除は専門業者へお任せください!~
アシナガバチの季節ごとの活動と駆除方法についてお伝えしましたがいかがだったでしょか。
まだ巣が小さいうちの駆除はそう難しくはありませんが、
最盛期の攻撃的になったアシナガバチの駆除を個人で行うのは危険が伴います!
できればハチ駆除専門業者に依頼することをお勧めします。
当社ではハチ駆除はハチ専門の熟練のスタッフが行います。
全ての作業は当社にてお任せいただき、安全のためお客様はご自宅内に避難していただいております。
蜂の巣をきれいに取る技術もありますので、お家の軒先や壁・天井など壊してしまうなどのトラブルも発生いたしません。
また、シーズン保証もつけておりますので、再発の際もご安心ください
※シーズン保証‥駆除したハチと同じ種類のハチが同じ場所に巣を作った場合、保証期間であれば無償で再度駆除いたします。(保証期間は施工した翌年の3月までになります)
プログラントの蜂駆除における5つのモットー
当社はハチなどの害虫駆除専門業です。蜂は巣に接近したものに対して警戒、攻撃する習性があります。
巣を見つけましたらそっとその場を立ち去りすぐにご連絡ください。
プロの駆除担当者が迅速に安全に蜂駆除、巣の撤去をいたします。
駆除作業の際にはお客様の安全は第一ですが、近隣や付近の通行されている方への二次被害がないよう最善の作業方法を考え作業いたします。
また天井裏や床下などに営巣を作り侵入口がない場合でも当社にて点検口を作成し駆除いたしますので何なりとお尋ねください。
その1 迅速な対応!
蜂の被害は人命にかかわる程に危険性が高く、迅速な対応が求められます。
プログラントではご依頼を受け付けた当日の対応を基本としています。
お客様の都合で当日の対応が困難な場合は最短の日程でお客様の対応しております。
その2 蜂を逃がさない工夫!
蜂の駆除においては、蜂を逃がさずに駆除する事が大切で、蜂は人間が近づくと警戒のため巣から出て攻撃準備に入ります。
出来るだけ蜂を巣から出さず、また出てきた蜂を出来るだけ駆除するために、蜂を刺激しないように接近する事はもちろんですが、
出てきた蜂に対しては大小のネットを使用して、蜂を一箇所に閉じ込め蜂の駆除施工致します。
その3 家屋や壁などに傷を付けない工夫!
天井裏、床下、壁の隙間などにも蜂は危険な巣を作ります。
このような場合、天井や壁を切り抜くなどの工事が必要になることがあります。
弊社では極力そのような工事を行わないように薬剤処理と蜂の出入り口の閉鎖をメインに作業を行います。
その4 機材を使用しての駆除!
プログラントでは蜂防護服、狭い隙間の奥や屋根裏、蜂の巣がある場合などは、
ファイバースコープの使用、閉鎖箇所に薬剤が充満した場合などは強制換気、
ハシゴが届かない場所には高所作業車を使用するなど、
様々な機材設備を用いてあらゆる場合に対応出来るようにしております。
その5 蜂駆除後も安心のサポート!
戻り蜂対策が特に重要です。 蜂の巣を除去しますと、巣があった場所に出かけていた蜂が戻ってくることがあります。
これを戻り蜂と我々は呼んでいます。
当社では、戻り蜂対策として、巣があった箇所に粘着マットを設置して対策を図ります。
戻り蜂が捕まったこの粘着マットは後日回収に伺います。
このように、駆除後もきちんと問題がないかチェックいたしますのでお客様においては満足いただけると思います。
プログラントではお客様第一主義としています。
お客様のご要望に出来るだけ添えられるよう休日・営業時間外でも対応できる体制を整えています。
問合せにつきましては、弊社ホームページのお問合せフォームに記入して頂くか、お気軽にお電話下さい。
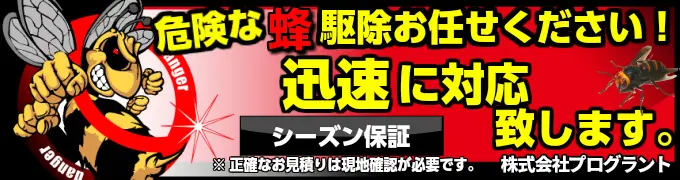
シロアリ駆除専門スタッフが
あなたのお悩みを解決いたします!!

- 羽アリが家から大量にでてきた
- 畳や床板など歩くとミシミシ音がするようになった
- 外壁や基礎部分にヒビや蟻道がある
- シロアリ保証期間が切れていた
- 脱衣所、洗面所などの床がブカブカする
- 家の周りや床下に木材(廃材)などを置いている
どのような疑問・質問にもすべてお応えします。
株式会社プログラントでは、現地調査点検・見積を無料で行っております。
まずはお気軽にご相談ください。
プログラントは安心と
信頼の5冠獲得





調査方法インターネット 調査
調査概要2022年2月 サイトのイメージ 調査
調査提供日本トレンドリサーチ
CONTACT
お問い合わせ
相談/見積り
完全無料
0120-778-114
24時間365日受付中

害獣・害虫・害鳥の スペシャリスト
藤井 靖光(Yasumitsu Fujii)
株式会社プログラント 代表取締役
拠点・連絡先
熊本本社
〒861-8002 熊本県熊本市北区弓削6丁目27-19
佐賀営業所
〒849-0937 佐賀県佐賀市鍋島3丁目9-5
お問い合わせ(代表)
緊急対応:7:00–22:00(年中無休/災害時は安全最優先の運用)
取扱分野
実績ハイライト
個人(藤井)調査実績
(1992–2025)
会社累計調査実績
(創業〜2025)
Google口コミ(熊本本社 334件)
Google口コミ(佐賀営業所 76件)
初回訪問スピード
最短当日訪問率 85%
報告書提出率
平均提出 10日
脚注:「個人=1992–現在」「会社=創業–現在(自社請負分)」
口コミ出典:Googleビジネスプロフィール[2025-08-12 時点]
定義:受付時間 7:00–16:00 の新規受付に対し 当日17:00までに訪問開始できた割合(警報発令・道路寸断日は母数除外)
主要資格・講習(抜粋)
- 建築物ねずみこん虫等防除業登録(熊本県)/熊市保30ね第1号
- 公益社団法人 日本しろあり対策協会/しろあり防除士[6名]/登録番号:13510
- 公益社団法人 日本しろあり対策協会/蟻害・腐朽検査士[2名]/登録番号:熊本県-17-0042
- 公益社団法人 日本木材保存協会/木材保存士[1名]
- 一般社団法人 住宅基礎コンクリート保存技術普及協会/住宅基礎コンクリート保存技術士[4名]/登録番号:J21-0211
- 一般社団法人 熊本県労働基準協会/特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者[2名]/登録番号:4350
- 高所作業車運転技能講習(コベルコ教習所)修了[4名]
- 一般社団法人 ペストコントロール技術者[1名]/登録番号:第2023-15号
- 公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター/防除作業監督者[1名]
- 狩猟免許(わな猟)[4名]/登録:P43-2019-N000460
ロープ高所作業(特別教育)について
当社はロープ高所作業(特別教育)修了者[4名]を配置。急勾配屋根・高所外壁・吹き抜けなどの高所作業において、事前リスクアセスメント/二重確保(バックアップ)/器具・アンカー点検/立入管理等の安全手順に基づき作業を実施します。
安全・法令・保証
法令遵守
鳥獣保護管理法/外来生物法/労働安全衛生法 等
賠償責任保険
あいおいニッセイ同和損保:対人/対物 各1億円(1事故あたり)
保証(要点)
対象・期間:
アライグマ/イタチ/ネズミ/シロアリ=5年、コウモリ=2年(※条件により最長10年)
適用条件:当社基準の封鎖+衛生施工を実施/(任意)年1回点検
除外:構造劣化・第三者工事・増改築・自然災害・餌付け 等
初動SLA:保証内再発のご連絡から 24時間以内に初動連絡/最短当日〜3日以内に訪問
安全実績
労災・薬剤インシデント 0件(直近36か月)
法令遵守:捕獲許可・鳥獣保護管理法 等の違反 0件(通算)
方針・運用ポリシー
方針:最新機材×従来機材/最新工法×従来工法/自社開発器具を融合したハイブリッド工法をケースに応じて最適化
施工記録の開示と保管・再発防止を徹底
編集・監修
「当サイトの技術記事は現場担当が執筆し、藤井 靖光が全件監修。公的資料・SDSを参照し、誤りは確認後速やかに訂正します。」
苦情対応
「受付 → 24時間以内に初動連絡 → 現地確認 → 是正 → 書面報告の順で対応します。」
安全・薬剤
「薬剤は用途・希釈・保管を社内SOPで管理。近隣・室内の隔離・換気・養生を徹底します。」
画像・記録の扱い
「施工写真・報告書は7年間保管。個人情報はマスキングのうえ事例公開します。」
会社FAQ
記事一覧へ