害獣が発生し、増加しているのはなぜか。

害獣が発生・増加し続ける最大の原因は、実は私達人間の生活の変化にあります。
私たちの生活、仕事、遊び方の変化によって、害獣が私たちの家に侵入する機会が増えています。
私たちは、食べ物や場所、水などで害獣を呼び寄せているのです。
そして、害獣が繁殖するための理想的な条件を、私たちはついうっかりと提供してしまっているのです。
この記事を読まれている方の中には、実際に害獣の被害に遭われている方もいらっしゃると思います。
結論から申し上げますと、害獣駆除はプロにお任せすることをオススメ致します。
害獣が多く発生し、増えてきているのは紛れもない事実です。
かと言って、大切な我が家を痛めつけている害獣を放置するわけにもいきません。
害獣たちが増えているという事は、それだけ被害に遭う可能性も比例して増しているということです。
害獣が増えている事態には各方面の専門家も警笛を鳴らしています。
弊社は、様々な大学や大学院の有識の教授などとお付き合いがあり、お話させて頂くことがございますが、専門家も危惧する事態なのは間違いありません。
決して不安を煽るわけではありません。
安心して下さい。
餅は餅屋というように、害獣にも害獣のプロフェッショナルが居ます。
今回の記事では、害獣の発生と増加に焦点を当てて専門的な観点のもとお伝えしていきます。
農作物を荒らす!?害獣が侵入する共通の要因

害獣が発生し続け、さらに増えていく理由はさまざまです。
最も一般的な要因のひとつは、農作物の被害です。
農家が作物を植えるために広大な土地を切り開くと、害獣にとって理想的な生息地が不注意にも出来てしまいます。
広々とした畑で天敵がいないため、害獣にとっての格好の餌場になります。
さらに、このような農場で栽培される作物は、害獣にとって大きな誘引となります。
彼らは作物の匂いに引き付けられ、長い距離を移動して作物を食べに来ます。
一度餌を見つけると、それがある限り何度でもやってきます。
害獣の侵入に共通するもう一つの要因は、人間の居住地です。
新しい土地に人が移り住むと、その土地に生息していた野生動物がいなくなることがよくあります。
その結果、害獣にとって理想的な環境となり、害獣の個体数を抑制する天敵が少なくなってしまうのです。
また、人間は気づかないうちに害獣の餌や隠れ家を提供していることもあります。
害獣の発生を防ぐためにできる最も重要なことは、害獣の生態や環境の変化への対応について学ぶことです。
そうすることで、潜在的な問題を早期に発見し、対策を講じることができるようになります。
害獣達が侵入する共通の原因を紐解いていきましょう。
人里の近くには天敵が少ないから
人間社会とその周辺には、無人の空間がほとんど存在しません。
そのため、害獣の天敵となるヘビやキツネ、ワシなどが敷地内にいることはほとんどありません。
天敵がいないということは、害獣にとって理想的な状況ということです。
屋根裏は天敵のリスクが少なく、気候も温暖なため、子育ての場所として好まれるケースがあります。
そのため、害獣は屋根裏で出産することが多いです。木酢液などを使って、屋根裏に侵入する前に害獣を追い出すようにしましょう。
エサが簡単に手に入るから
害獣が発生する最も大きな原因のひとつは、おいしい餌がすぐに手に入ることです。
つまり、人間社会が害獣の餌場になっているのです。
害獣の立場からすれば、餌を得るために苦労していたものが、人間社会にいれば安全に手軽に得れるため、これ以上の利点はありません。
また、人里近くには食べ物が多いため、害獣は出て行く理由が少なく、そのまま居ついてしまう可能性が高いのです。
害獣は人間の食べ物にも寄ってきます。
食べかすから生ゴミまで、人が捨てたものなら何でも食べます。
生ゴミを適切に処理することで、害獣の発生を抑えることができます。
害獣が美味しい食べ物を手に入れられるのだから、人間社会に行くのは必然と言えば必然のことです。
水源が豊富だから
人々の生活圏は、ほとんどの場合、水資源に恵まれています。
これは、水が生き物の生存に不可欠な要素だからです。
水がなければ生きていけないのは、害獣達も同じです。
適切な食料供給源に水場があれば、そこに住処を作るのは当然のことです。
水資源が増えれば、害獣の量も増えるということ。
つまり、人が増えれば増えるほど、害獣も増えるのです。
人が水資源を使うことが増えることで、害獣が繁殖しやすい環境が整うからです。
鳥獣保護管理法があり許可なくに駆除することはできないから
鳥獣保護管理法は、一部の害獣を保護する法律です。
鳥獣保護管理法は、動物とその生息地を保護することを目的とした法令です。
被害害獣がこの法律の対象になっている場合、一般の人が自分の権限で駆除することはできません。
害獣を駆除するためには、煩雑な手続きを経て許可を得る必要があります。
動物やその生息地を守るために作られた法律です。
法律により、許可なく動物の駆除をすることは困難です。
これが近年、害獣が増加している原因の一つです。
活動範囲の拡大
研究者によると、この100年の間に、地球の気温は0.85℃上昇したそうです。
その結果、山の降雪量は減少しています。
降雪量の減少に伴い、動物の行動範囲が広がり、害獣が人里に現れるようになりました。
近年、自然災害の発生件数も増加しています。
これは、気候変動の影響と考えられています。
自然災害が発生すると、動物は住み慣れた場所を離れ、人間と接触せざるを得なくなります。
害獣と呼ばれる動物たち

害獣は厄介者ではありますが、生態系において重要な役割を担っていることを忘れてはいけません。
害虫の発生を抑制し、栄養分を土壌に還元してくれます。
場合によっては、捕食者の食料源となることもあります。
一般的に害獣と呼ばれる動物たちの一部を紹介します。
イタチ

イタチは、イタチ科の小型肉食哺乳類です。
日本には主に2種類のイタチが生息しています。
ニホンイタチとシベリアイタチ(チョウセンイタチ)です。
ニホンイタチ…ニホンイタチは日本原産ですが、地域によっては侵略的外来種とされています。
ネズミを退治するニホンイタチは、もともといなかった北海道や宮古島にネズミ対策として持ち込まれました。
ニホンイタチは、地域の在来種を食べるようになり、地域によっては「国内由来の侵略的外来種」とまで言われるようになりました。
チョウセンイタチ…元々日本にいた在来種であるニホンイタチは現在減少しているため、害獣被害や街中で見かけるイタチはほとんどがチョウセンイタチです。
チョウセンイタチは、”シベリアイタチ”、”タイリクイタチ “とも呼ばれます。
日本にいつ、どのように持ち込まれたかは不明であり、戦後、毛皮を目的に輸入された後、九州に運ばれて荷物に紛れ込んだと言われています。
イタチは非常に適応力の高い生物として知られており、近年、人間の生活や活動の変化により、イタチが人里に出没することが多くなっています。
その主な理由は、イタチが人里に来れば豊富な食料を得られることを知ったからです。
イタチは雑食で、ネズミや鳥、爬虫類、腐肉など、何でも食べます。
イタチは常に食べ物を探しているためまた、鶏小屋や鳥の餌箱を荒らすこともあります。
イタチが人里に現れるようになったもう一つの理由は、人間がイタチに隠れる場所を与えてしまったという点です。
イタチは屋根裏などの暗い場所や人里離れた場所に住み着くようになります。
イタチが人里に出没するようになったのは、人間を恐れなくなったからです。
かつて、イタチが人間と接触するのは、狩猟や罠にかかったときだけでした。
しかし、イタチが人間の存在に慣れてきたことで、人間を怖がらなくなったのです。
以上の理由からイタチの目撃情報が増えています。
ネズミ

ネズミは、餌と隠れ家があることで人里に引き寄せられます。
定期的に餌がもらえることを知ると、再び訪れるようになり、害獣被害の増加は、人々が室内で過ごす時間が長くなったためと考えられています。
そのため、害獣が餌や隠れ家に現れる機会が増えているのです。
さらにまた、冷暖房の普及など人間のライフスタイルの変化により、ネズミが好む新たな環境も生まれています。
ネズミもまた、人里の食料や住居に引き寄せられるようにやってきます。
建物の暖かさにも惹かれるため、より住みやすい環境を求め家屋へ侵入します。
冷暖房の普及など人間のライフスタイルの変化も、ネズミが好む新たな環境を生み出しています。
ネズミが電線をかじって火事になるケースもあります。病気を蔓延させることも知られています。
人間のライフスタイルの変化により、ネズミの生息域は拡大しています。
アライグマ

アライグマは、北米が原産の生き物で、人里に最も多く生息する動物の一つであり、人間の周りに住むことによく適応しています。
アライグマは何でも食べるので、食べ物を求めてゴミ箱をあさることがよくあります。
アライグマはまた、ペット用のドアや安全でない窓やドアから家の中に入ることでも知られています。
アライグマは可愛い見た目とは相反して、ものすごく凶暴な生き物です。
特に身の危険を感じると、人間を襲って噛み付くことが知られています。
さらに、アライグマは狂犬病などの病気の媒介をすることでも有名です。
また、アライグマについているマダニからSFTSという重大な病気に感染する恐れもあります。
この病気は発熱、下痢、嘔吐を引き起こし、場合によっては死に至ることもあります。
アライグマの特徴の一つに、凄まじい繁殖力が挙げられます。
妊娠率は脅威の100%というアライグマ。死ぬまで出産することが可能です。
アライグマの数を減らす唯一の方法は、駆除です。
メスのアライグマは、一生の間子供を持つことができます。一回の出産では4~6匹の子供を産みます。
アライグマの繁殖率の高さと寿命の長さが、数を増やし続けている大きな理由です。
たとえアライグマの半分を殺処分したとしても、その数はすぐに元に戻ってしまいます。
それほど深刻な状況というわけです。
コウモリ

コウモリは世界中に数多くの種類が居ますが、日本で家屋に住み着くのは主にアブラコウモリの1種類だけです。
コウモリは屋根裏に住むことが多いです。
場合によっては、家屋の居住区に住み着くこともあります。
コウモリは一般的に人体に無害ですが、その糞にはウイルスが含まれており、人によっては重度の呼吸器疾患を引き起こす可能性があります。
コウモリは構造物の隙間で、特に春先の少し暖かい日や秋には、人間の耳でも「キーキー…」と金属音が聞こえることがあります。
コウモリのねぐらの真下には、糞がよく散乱しています。
コウモリを駆除する方法は侵入に使う可能性のある開口部はすべて塞ぎましょう。
ドアや窓の周りの隙間、壁や天井の穴などです。
また、ペットの餌やゴミなど、引き寄せる可能性のある餌は取り除いておく必要があります。
ハクビシン

ハクビシンは白い鼻筋が特徴的です。
熱帯アジアやアフリカに生息する小型から中型の哺乳類であり、ハクビシンは雑食性で、植物も動物も食べます。
夜行性で、夜間に活動します。
ハクビシンは餌があるため、人里に集まってきます。
ハクビシンは生ゴミに惹かれ、よくゴミ箱をあさり、餌を探します。
ハクビシンはペットフードや果物、野菜も食べます。
ハクビシンは、SARSウイルスを保有しており、このウイルスはハクビシンから発生し、ヒトに感染したと考えられています。
このため、ハクビシンは人間にとって迷惑な存在になる可能性があります。
イタチが発生する原因とその対処方法

イタチの個体数は様々な理由で爆発的に増えることがあります。
雑食であり、獲物が見つけやすく、豊富にある状況であれば、利用します。
そんなイタチの発生原因と対処方法を見ていきましょう。
イタチの発生原因
イタチの個体数は、定期的に個体数の増加と減少のサイクルを繰り返しています。
このような個体数の変動の理由は完全には解明されていませんが、食料が不足すると、イタチたちはより激しく食料を争奪し、時には共食いに走ることもあり、その結果、イタチ全体の個体数が減少することもあります。
しかし、餌が豊富にあると、イタチは繁殖が早くなり、個体数が急激に増加します。
天敵がいないとイタチが野放しに繁殖し、個体数が爆発的に増え、これらの要因が重なると、イタチの数は増加します。
繁殖力もとても強く、妊娠率もほぼ100%です。
メスよりもオスのほうが行動範囲が広く、オスは繁殖期になるとメスのいるところへ現れて交尾をして妊娠させていきます。
交尾は通常12月下旬から2月上旬に行われ、その20〜30日後に4〜6頭の子イタチが誕生します。
イタチ科の動物の寿命は、野生では2〜3年ですが、飼育下ではもっと長生きするものもいます。
イタチの対処方法
イタチやその他の害獣は、多くの住宅所有者にとって共通の問題です。
これらの害獣は、家や財産に損傷を与える可能性があります。
イタチなどの害獣を駆除するためには、いくつかのポイントがあります。
まず、イタチがどうやって家の中に入ってきているのかを把握することです。
イタチは非常に小さな隙間からも入ってくることができるので、家の周りに亀裂や穴がないか確認することが大切です。
イタチの居場所を突き止めたら、イタチの侵入経路となる開口部を塞ぐことが重要になってきます。
2つ目のポイントは、イタチがどのような餌を求めているかということです。
イタチはネズミやウサギなどの小動物に寄ってきて、餌場がある場合、除去する必要があります。
3つ目のポイントは、イタチのための罠を設置することです。
罠には様々な種類がありますので、自分に合ったものを見つけることが大切です。
ネズミが家に侵入する理由とその対処方法

ネズミは世界で最も一般的な害獣の一つであり、いつまでもいなくなる気配はありません。
実は、さまざまな要因でネズミの侵入は悪化の一途をたどっているのです。
ネズミが発生し続ける最も明白な理由は、私たちがネズミに食べ物を与え続けていることです。
もちろん、私たちはわざとやっているわけではありません。
ただ、現代のライフスタイルは多くの生ゴミを生み出しており、ネズミはそれを利用するのがとても上手なのです。
また、ネズミが身近な存在になりつつあることも要因のひとつです。
人間の居住地が密集するようになったことで、ねずみの生息地が増えました。
そんなネズミの発生原因と対処方法についてお話していきます。
ネズミの発生原因
ネズミは食料や避難場所を求めて人里に集まってきます。
私たちは知らず知らずのうちに、ネズミが生存・繁栄するために必要なものを与えてしまっているのです。
ネズミが発生する主な原因は、餌と水が手に入るかどうかです。
ネズミは何でも食べますが、特に穀物や穀類などの炭水化物の多い食品を好みます。
また、生きるために水を必要とするので、新鮮な水のある場所にはネズミが寄ってきます。
また、ネズミは人間の活動が多いところにも寄ってきます。
これは、人間が気づかないうちにネズミの餌を落としたり、隠れ家を提供していることが多いためです。
ネズミはすぐに繁殖できるので、餌と隠れ家が豊富にあるところでは、すぐに繁殖してしまいます。
そのため、短期間でネズミがはびこることになります。
また、ネズミは病気の媒介者でもあり、人に害を及ぼすこともあります。
尿や糞で病気を移したり、人に噛み付いたりします。
ネズミの対処方法
そんなネズミの侵入を防ぐためにできることはいくつかあります。
最初のステップは、家への侵入口となる可能性のある場所を特定することです。
これらは、基礎のひび割れ、またはパイプが家に入る開口部である可能性があります。
これらの潜在的な問題の領域を発見したら、コーキング、スチールウール、または耐久性のある材料の別のタイプでそれらを封じます。
さらに、ネズミを捕まえるために家に罠を設置することができます。
もし、深刻な問題の場合は、プロの害虫駆除業者に依頼する必要があるかもしれません。
プロは、問題の原因を特定し、迅速かつ効率的にそれを排除することができます。
また、ネズミを呼び寄せる可能性のある餌を排除する対策も必要です。
食べ物は密閉容器に入れ、床に置かないようにしましょう。
食べこぼしはすぐに片付け、ペットフードを一晩中出しておかないようにしましょう。
家の中をできるだけ清潔に保つよう心がけましょう。
そうすることで、ネズミの居場所を探しているネズミを誘うことが少なくなります。
アライグマが発生する要因と対処方法

アライグマは、昔から人間と共存してきた動物です。
また、餌を求めて人里に侵入することが多い動物の一つでもあり、その主な理由は、人間の生活の変化により害獣被害が増加したためです。
私たちが毎日捨てているゴミは、アライグマの一家が数ヶ月間、十分に食べていけるだけの量です。
私たちがペットのために出しているエサにもアライグマは寄ってきます。
アライグマの生息地に家を建てることで、アライグマに場所を提供しているのです。
害獣の被害を防ぐ最善の方法は、誘引物を取り除くことです。
ゴミは密閉できる容器に入れる、ペットの餌は出さないなどです。
また、家の周りの環境も清潔に保つようにしましょう。
アライグマの発生原因
アライグマは、人里に出てくると、抑制がきかなくなり、野放しに増殖してしまいます。
アライグマが大発生する主な理由は、以下の通りです。
1.餌を与えるアライグマは人間や動物に寄ってくる。
2.アライグマは、人里で一年を通して定期的に餌をもらえることを学習する。
3.食料が不足すると、アライグマは食料を調達するために人里にやってくる。
4.アライグマは、ゴミが多い場所に集まる。
アライグマは警戒心があまりないため、人間を怖がりません。
アライグマの対処方法
害獣が発生・増加し続ける主な理由は、人里で年間を通じて定期的に餌がもらえることを知り、餌が不足すると人里にやってきて餌を調達するためです。
ゴミの多いところに集まるので、さらに問題が悪化します。
アライグマの個体数を抑制する最善の方法は、餌の供給源と隠れ家を取り除くことです。
しかし、これは「言うは易く行うは難し」であることが多いです。
アライグマは非常に順応性が高く、何でも食べるので、すべてのアライグマを除去するのは難しいかもしれません。
アライグマを遠ざけるには、食べ物や隠れ家がない状態にすることが一番です。
アライグマを遠ざけるためのいくつかのヒント。
ゴミ、ペットフード、鳥のエサの種子などのすべての食糧源を、アライグマから遠ざけましょう。
穴や屋根裏への開口部を密封しましょう。
敷地内を清潔に保ち、ゴミがないようにする。
アライグマの問題を抱えている場合は、アライグマを駆除し、アライグマが戻ってくるのを防ぐために専門の駆除業者へ連絡することをオススメいたします。
コウモリが発生する原因と対処方法

コウモリが発生・増加し続ける最大の理由は、人里で一年を通して定期的に餌が得られることを知っているからです。
屋根裏や地下室など、人が多く集まる場所にコウモリが定住することが多いため、問題が深刻化しています。
コウモリの発生原因
コウモリの大発生の主な原因は、餌の入手が可能になることです。
コウモリは、人里など定期的に餌が供給される場所に集まってきて、餌を求めて人里にやってきたコウモリは、一年を通して定期的に餌がもらえることを知ります。
そのため、コウモリは人里やその周辺によく来るようになり、その結果、コウモリは人里やその周辺に住み着くようになります。
コウモリは餌に集まるだけでなく、隠れ家となる場所にも集まってきます。
コウモリは屋根裏や地下室など、人が集まる場所をねぐらにすることが多く、問題をより深刻にしています。
コウモリの対処方法
屋根裏のコウモリを駆除する方法
コウモリは、日本でも一般的な害獣の1つです。
コウモリはしばしば屋根裏部屋でねぐらを作り、大切な家に深刻な脅威をもたらす可能性があります。
できるだけ早くコウモリの家を駆除するための措置を取ることが重要です。
屋根裏にコウモリを取り除くことができるいくつかの異なる方法があります。
1つの方法は、コウモリの忌避剤を使用することです。
コウモリの忌避剤は、ほとんどのホームセンターで購入できます。
また、水と酢を同量ずつ混ぜて、コウモリ忌避剤を自作することもできます。
別の方法は、バットトラップを使用することです。バットトラップは、ほとんどのお店で購入いただけます。
コウモリを遠ざける最善の方法はコウモリの餌となるものを排除する。
また、コウモリ忌避剤を使用することもできますが、これは必ずしも効果的ではありません。
ゴミ箱、ペットの餌、鳥の餌など、餌になりそうなものを密閉することで可能になります。
また、コウモリの隠れ家となるようなものを取り除き、家を清潔に保つことも重要です。
ハクビシンが発生する原因と対処方法

ハクビシンは、農作物に引き寄せられ、何でも食べてしまうのです。
また、ハクビシンはゴミ捨て場にも引き寄せられ、そこで餌を見つける。
ハクビシンは小型の哺乳類、爬虫類、鳥類も食べます。
ハクビシンの発生原因
ハクビシンが発生する理由はさまざまです。最も重要なのは、人里やその周辺に餌場が発生し続けることです。
ハクビシンは食べ物の匂いに引き寄せられるので、餌場がある限り何度でもやってきます。その他にも重要な要素があります。
ハクビシンが外敵から安心して身を隠せるような、くぼんだ木や密集した草木などの隠れ家が存在すること。
天敵がいないこと。
ハクビシンは天敵が少ないので、ハクビシンを捕食する動物がいないと、ハクビシンの個体数が増加してしまうことがある。
ハクビシンの対処方法
ハクビシンは夜行性なので、罠を仕掛けるのは夜間が最適です。
ゴミ箱の蓋をしっかり閉め、家の周りから餌になりそうなものを取り除いておきましょう。
もしハクビシンが日中歩き回っている場合は、病気やケガの可能性がありますので、専門業者に連絡してください。
ハクビシンの捕獲は難しいことではありませんが、根気が必要です。
最も重要なことは、適切な餌を使用することです。
ハクビシンは強い匂いに引きつけられるので、イワシをいくつか置いておくとよいでしょう。
イワシがない場合は、腐った肉や魚でもかまいません。
エサは、ハクビシンがエサにありつくために罠の中に入らなければならないように、罠の奥に設置します。
罠に餌をつけたら、あとは待つだけです。
数日かかることもあります。
ハクビシンを捕まえたら、慎重に扱うことが大切です。
ハクビシンは攻撃的で、身の危険を感じると噛みつくことがあります。
ハクビシンが戻ってこないようにし、または、潜在的な危険にさらされないようにします。
そもそもハクビシンが家に入るのを防ぐことです。
すべての食料源に接触できないようにし、ゴミ箱はしっかりと密閉してください。
害獣の原因は人間?
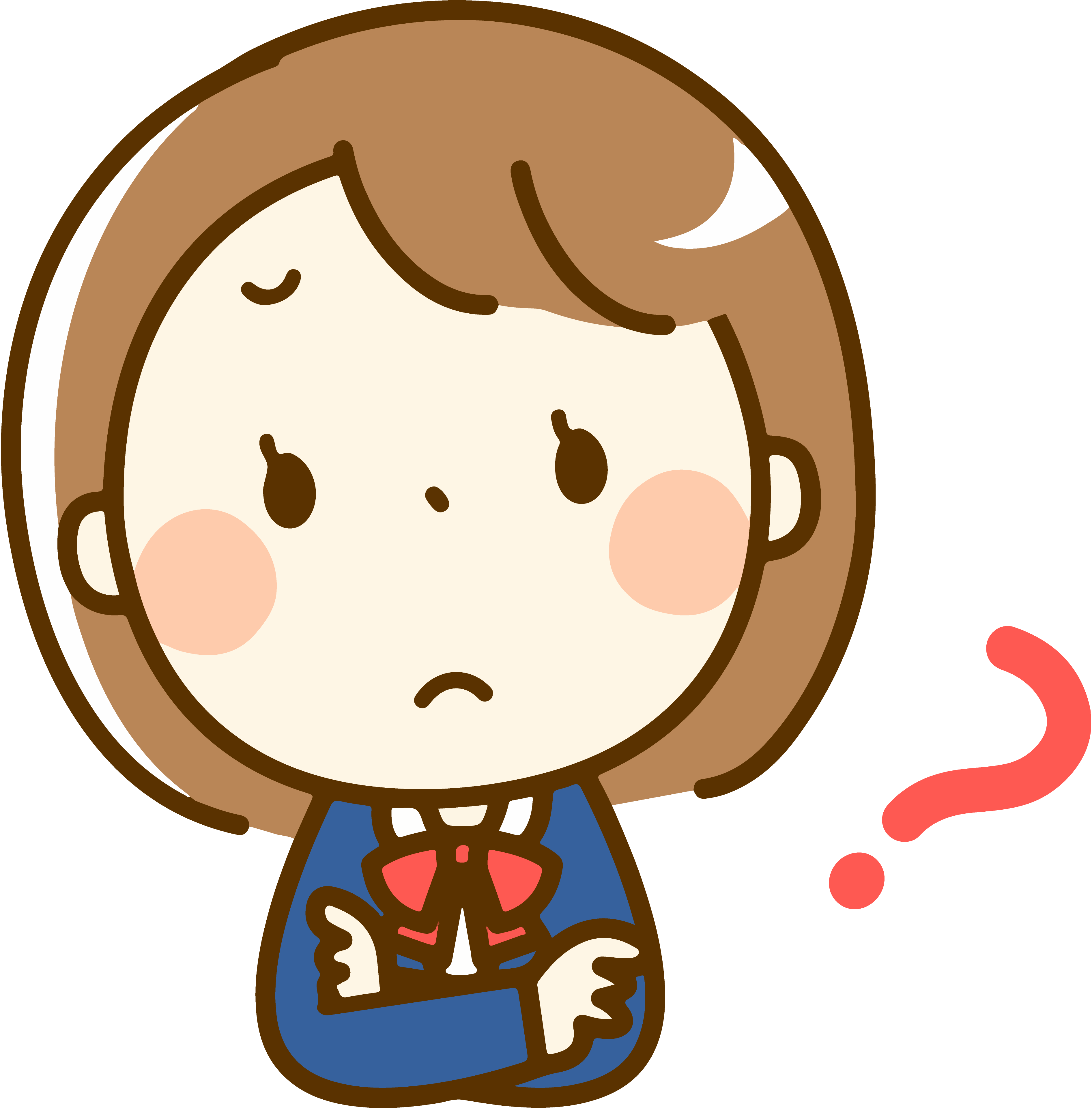
害獣の主な原因は人間なのです。
その理由はいくつかあります。
第一に、人間の生活の変化が害獣の侵入の原因。
第二に、人間が知らず知らずのうちに野生動物に餌を与え、引き寄せ、隠れ家を提供していることも、害獣が発生・増加し続ける理由の一つです。
動物が人里にやってくるときその結果、1年を通じて定期的に餌をもらえることがわかり、生き残りやすくなります。
そのため、生存と繁殖が容易になるのです。
私たちの生活様式が変わらない限り、害獣はこれからも問題であり続けるでしょう。
この問題を解決するためには、野生動物に対する私たちの考え方を変えなければなりませんし、私たちの生活様式を変えなければなりません。
経済発展の結果、都市が発展し、農村部と都市部の距離が縮まっています。
そのため動物が人間と接触する機会が増えています。
生活様式が変わり、以前より動物との距離が近くなっているのです。
かつての人々は小さな村に住み、狩りをし、食料を集めていました。
彼らは自然を深く敬い、人間と動物のバランスを理解していたのです。
現在では都市に住む人々は、自然との接点が少なく、動物が公衆衛生に及ぼす危険性を認識していません。
その結果、動物に噛まれたり、引っかかれたりすることが多くなり、動物から病気に感染する危険性が高まっているのです。
害獣の個体数が増えているのには、さまざまな理由があります。
ひとつは、農業や開発などによって景観が大きく変化したこと。
その結果、害獣にとって理想的な生息地が新たに生まれました。
近年は侵略的な外来種が要因となっています。
これらの動物は、私たちの生態系に本来生息していないものであり、地域の野生動物に悲惨な結果をもたらす可能性があります。
コロナ禍で害獣が急増?!

このたびの新型コロナウイルスまん延により、多くの人が生活習慣や労働習慣の変化を余儀なくされています。
その結果、人里やその周辺で見られる害獣の数が増えているのです。
害獣が急増した理由はいくつかあります。
1.家にいる時間が長くなったこと。
2.コロナ禍をきっかけに失業が多くなったこと。
3.コロナウイルスまん延防止措置のためにサービスの利用が出来なかったこと。
1つ目は、家にいる時間が長くなったこと。
つまり、害獣が食べることのできる餌が増えます。
仕事や介護など、他のことに気を取られ、家の中を清潔に保つことに気が回らないことも多く、害獣が侵入し、住み着くきっかけとなるのです。
2つ目に、コロナ禍をきっかけに多くの人が仕事を失いました。
その結果、害獣駆除サービスにお金を払う余裕がなくなってしまったのです。
3つ目は、コロナウイルスの蔓延を防ぐために施された封鎖措置により、害虫の駆除が難しくなったことです。
例えば、害獣駆除サービスを呼びにくくなったことや害獣駆除製品の購入のためこれらの要因はすべて、最近の害獣の個体数の増加につながっています。
害獣の増加は、いつまで経ってもなくならない問題です。
どちらかというと、今後悪化する可能性が高いだけです。
この問題に対処する最善の方法は、そもそも害獣が家に侵入するのを防ぐ措置をとることです。
これには、家を清潔に保つことが含まれます。
害獣を寄せ付けないように食品を保管することも大切です。
害獣が発生したら、すぐに対処することが大切です。
長引けば長引くほど、駆除が難しくなります。
必ず害獣駆除のプロに駆除を依頼してください。
野生生物の自然死が減った理由

野生で暮らす動物にとって、食料はより予測しにくく、まばらです。
食料不足で餓死したり、冬場や収穫期に抵抗力が弱まって病気になり、死んでしまうこともあり、自然死亡とは、このことを言います。
冬、食料が不足すると、野生動物は血眼になって食料を探します。
人間にとっては不潔な、虫に食われたゴミのようなものでも、害獣にとっては、山で見たこともないほど素晴らしく、美味しい、栄養価の高い作物なのです。
柑橘類にいたっては甘くて美味しくて、ビタミンCが豊富な食べ物です。
一日中、餌を探している野生動物が、偶然にジャガイモが捨ててある場所に出会ったらどうなるでしょう。
少しの時間でお腹を満たすことができるバイキングレストランとも言いますか。
野生動物は、人間の住む場所における食料の価値を理解し始めるのです。
野生では、大型の肉食獣や悪天候、病気など、さまざまな危険因子があります。
人間の住む場所では、動物が食料や居場所を容易に見つけることができるため、その数は必然と増加します。
最近の害獣の増加の主な理由は、彼らの自然死の数が減少したためだと言われています。
これまで述べてきたことからわかるように、野生動物の自然死亡率が低下している理由はいくつかあります。
第一は、人間による野生動物への餌付けです。
餌を求めて人里にやってきた動物たちは、一年中定期的に餌がもらえることを知ります。
その結果、人間に対する恐怖心がなくなり、人間の存在に慣れます。
被害にお困りの方はすぐに業者へ相談を!

害獣の発生が増加した理由はさまざまです。
都市化・郊外化などの人間生活の変化により、人と野生動物との接触が多くなっています。
かつて野生であった地域に人間が進出してきたことで、野生動物が人間やその食料源とより密接に接触するようになりました。
人間の人口が増えれば増えるほど、害獣が食べることのできる餌の量も増える。
私たちは知らず知らずのうちに、野生動物に餌を与え、引き寄せ、隠れ家を提供しているのです。
食料と住居の確保が可能になったことで、害獣の数が増加した。また、人間による自然生息地の破壊は、多くの動物を人間とより密接に接触させるようになった。
このような変化の結果と、人と接触する動物が増え、害獣によるトラブルが増加しました。
害獣を効果的に駆除するためには、害獣の発生が増加した理由を理解することが重要です。
理解した上で、害獣が自宅に侵入する可能性を減らすための対策を講じることができます。
もちろん、害獣駆除を専門に行う業者に依頼することもできます。
害獣を駆除し、再発を防止するためのサポートをしてくれるでしょう。
弊社では、専門知識を有した経験豊富なスタッフが丁寧な作業で害獣を防除し、再侵入を許しません。
また、現地調査とお見積りは無料にて行っております。
ご安心して調査を受けられると良いと思います。

また、弊社は九州北部エリアの害獣駆除業者で初の5冠を獲得致しました。

Googleクチコミ★★★★★(4.8/5.0)という高評価をいただいております。
顧客満足度調査においても97.5%(2021年度自社調べ)の高い評価をいただいております。

調査・お見積りからお気軽にご相談下さい。
【まとめ】害獣の発生原因の解明と対策
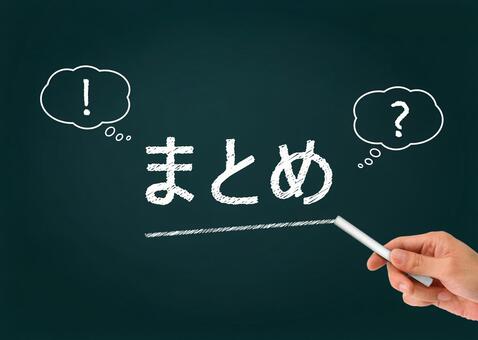
ここまで、害獣が増加する原因についてお話してきました。
我々人間こそが害獣を生み出す主な原因なのです。私たちの暮らしぶりや食べ物、出すゴミが、野生動物を引き寄せるのです。
餌を求めて人里にやってきた動物たちは、一年を通して定期的に餌がもらえることを知ってしまう。
その結果、害獣の数が増えてしまうのです。
害獣の数を減らすためには生活を変えましょう。
ゴミを少なくすること。家に動物が入らないようにすることも必要です。
そうすれば、害獣を減らすことができるのです。害獣を減らすためにさらに、行政の対策も必要です。
動物が人間と接触しにくくすること。
そのためには、野生動物への餌付けを制限することも一つの方法です。
そうすれば、動物が人里に馴染みにくくなり、害獣も減ります。
私たちの生活習慣が動物を呼び寄せ、それが害獣を増やすことにつながっているのです。害獣を減らすためには、生活習慣を改めることが必要です。野生動物の飼育を制限するなどの行政的な措置も必要です。
被害にお困りの際は、専門の駆除業者へご相談下さい。
シロアリ駆除専門スタッフが
あなたのお悩みを解決いたします!!

- 羽アリが家から大量にでてきた
- 畳や床板など歩くとミシミシ音がするようになった
- 外壁や基礎部分にヒビや蟻道がある
- シロアリ保証期間が切れていた
- 脱衣所、洗面所などの床がブカブカする
- 家の周りや床下に木材(廃材)などを置いている
どのような疑問・質問にもすべてお応えします。
株式会社プログラントでは、現地調査点検・見積を無料で行っております。
まずはお気軽にご相談ください。
プログラントは安心と
信頼の5冠獲得





調査方法インターネット 調査
調査概要2022年2月 サイトのイメージ 調査
調査提供日本トレンドリサーチ
CONTACT
お問い合わせ
相談/見積り
完全無料
0120-778-114
24時間365日受付中

害獣・害虫・害鳥の スペシャリスト
藤井 靖光(Yasumitsu Fujii)
株式会社プログラント 代表取締役
拠点・連絡先
熊本本社
〒861-8002 熊本県熊本市北区弓削6丁目27-19
佐賀営業所
〒849-0937 佐賀県佐賀市鍋島3丁目9-5
お問い合わせ(代表)
緊急対応:7:00–22:00(年中無休/災害時は安全最優先の運用)
取扱分野
実績ハイライト
個人(藤井)調査実績
(1992–2025)
会社累計調査実績
(創業〜2025)
Google口コミ(熊本本社 334件)
Google口コミ(佐賀営業所 76件)
初回訪問スピード
最短当日訪問率 85%
報告書提出率
平均提出 10日
脚注:「個人=1992–現在」「会社=創業–現在(自社請負分)」
口コミ出典:Googleビジネスプロフィール[2025-08-12 時点]
定義:受付時間 7:00–16:00 の新規受付に対し 当日17:00までに訪問開始できた割合(警報発令・道路寸断日は母数除外)
主要資格・講習(抜粋)
- 建築物ねずみこん虫等防除業登録(熊本県)/熊市保30ね第1号
- 公益社団法人 日本しろあり対策協会/しろあり防除士[6名]/登録番号:13510
- 公益社団法人 日本しろあり対策協会/蟻害・腐朽検査士[2名]/登録番号:熊本県-17-0042
- 公益社団法人 日本木材保存協会/木材保存士[1名]
- 一般社団法人 住宅基礎コンクリート保存技術普及協会/住宅基礎コンクリート保存技術士[4名]/登録番号:J21-0211
- 一般社団法人 熊本県労働基準協会/特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者[2名]/登録番号:4350
- 高所作業車運転技能講習(コベルコ教習所)修了[4名]
- 一般社団法人 ペストコントロール技術者[1名]/登録番号:第2023-15号
- 公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター/防除作業監督者[1名]
- 狩猟免許(わな猟)[4名]/登録:P43-2019-N000460
ロープ高所作業(特別教育)について
当社はロープ高所作業(特別教育)修了者[4名]を配置。急勾配屋根・高所外壁・吹き抜けなどの高所作業において、事前リスクアセスメント/二重確保(バックアップ)/器具・アンカー点検/立入管理等の安全手順に基づき作業を実施します。
安全・法令・保証
法令遵守
鳥獣保護管理法/外来生物法/労働安全衛生法 等
賠償責任保険
あいおいニッセイ同和損保:対人/対物 各1億円(1事故あたり)
保証(要点)
対象・期間:
アライグマ/イタチ/ネズミ/シロアリ=5年、コウモリ=2年(※条件により最長10年)
適用条件:当社基準の封鎖+衛生施工を実施/(任意)年1回点検
除外:構造劣化・第三者工事・増改築・自然災害・餌付け 等
初動SLA:保証内再発のご連絡から 24時間以内に初動連絡/最短当日〜3日以内に訪問
安全実績
労災・薬剤インシデント 0件(直近36か月)
法令遵守:捕獲許可・鳥獣保護管理法 等の違反 0件(通算)
方針・運用ポリシー
方針:最新機材×従来機材/最新工法×従来工法/自社開発器具を融合したハイブリッド工法をケースに応じて最適化
施工記録の開示と保管・再発防止を徹底
編集・監修
「当サイトの技術記事は現場担当が執筆し、藤井 靖光が全件監修。公的資料・SDSを参照し、誤りは確認後速やかに訂正します。」
苦情対応
「受付 → 24時間以内に初動連絡 → 現地確認 → 是正 → 書面報告の順で対応します。」
安全・薬剤
「薬剤は用途・希釈・保管を社内SOPで管理。近隣・室内の隔離・換気・養生を徹底します。」
画像・記録の扱い
「施工写真・報告書は7年間保管。個人情報はマスキングのうえ事例公開します。」
会社FAQ
記事一覧へ
関連記事
2025.08.04
佐賀県神埼市 イタチ駆除5冠達成! お客様喜びの声 プログラント
コウモリ地域別害獣駆除2025.09.19
福岡県大木町 コウモリ駆除5冠達成! お客様喜びの声 プログラント
ネズミ地域別害獣駆除2025.08.23
熊本県阿蘇郡高森町 ネズミ駆除5冠達成! お客様喜びの声 プログラント
イタチ地域別害獣駆除2025.08.09
熊本県人吉市 イタチ駆除5冠達成! お客様喜びの声 プログラント
アライグマ地域別害獣駆除2025.08.23
福岡県大刀洗町 アライグマ駆除5冠達成! お客様喜びの声 プログラント
ネズミ地域別害獣駆除2025.08.23
熊本県上益城郡御船町 ネズミ駆除5冠達成! お客様喜びの声 プログラント


















